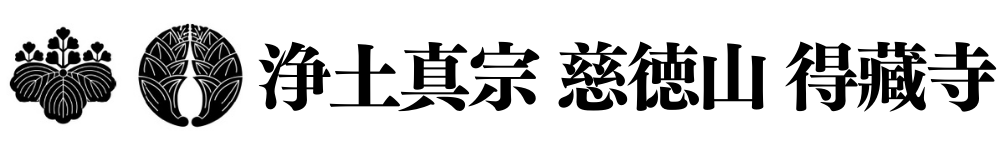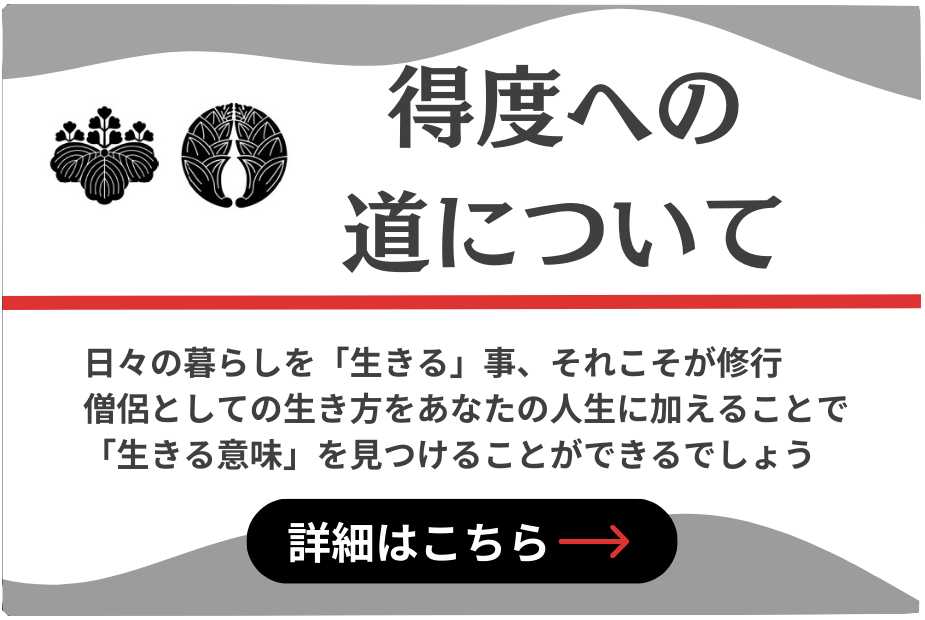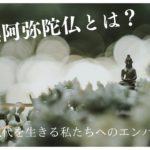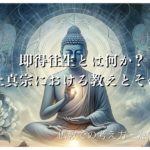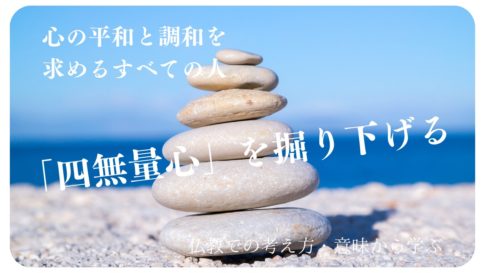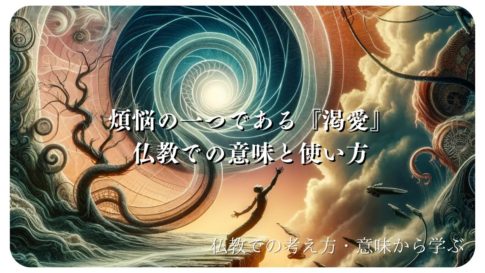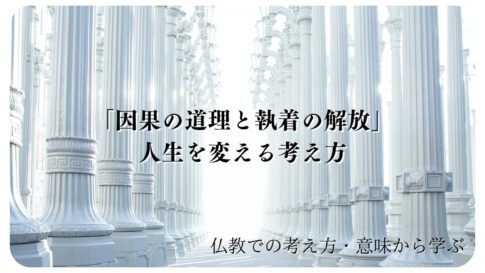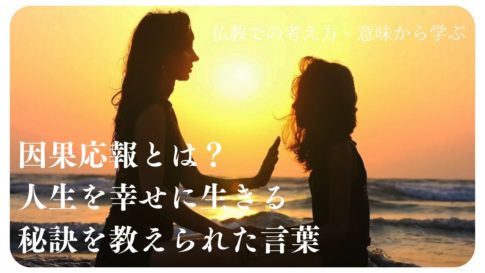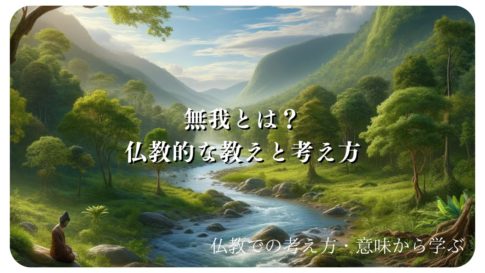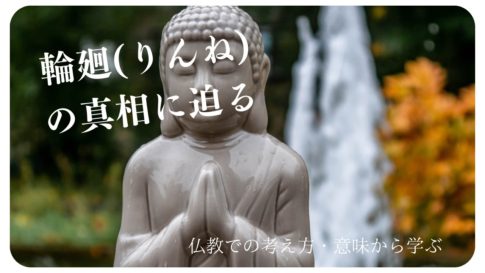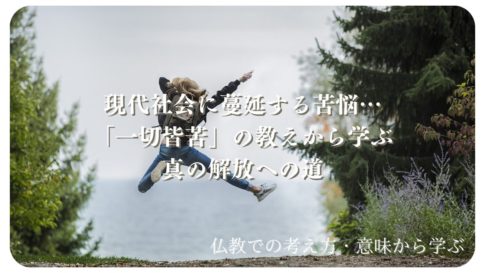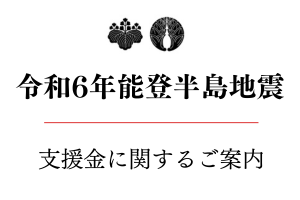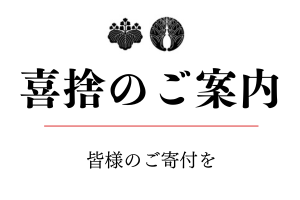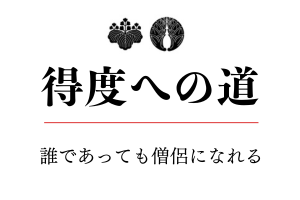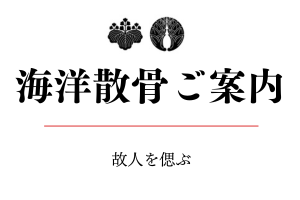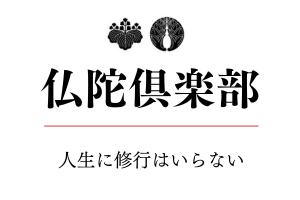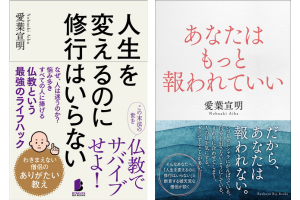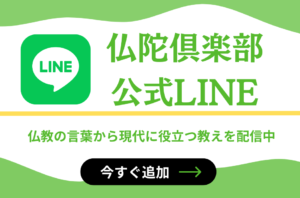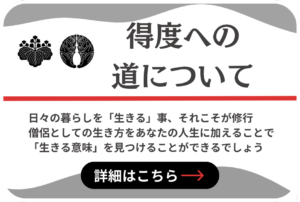「自他不二」とは、簡単に言えば「自分と他人は基本的に一体であり、切り離すことはできない」という考え方です。
現代社会において、私たちはしばしば自分と他人を別個の存在として捉え、それが人間関係における多くの誤解や対立の原因となっています。しかし、「自他不二」の理解によって、私たちはより調和のとれた、健全な人間関係を築くことができるのです。
この記事では、「自他不二」という概念を深く掘り下げ、それがどのようにして私たちの人間関係に影響を与え、改善に繋がるのかを探求します。私たちが他者を理解し、共感する能力は、「自他不二」の考え方に根ざしています。この考え方は、私たち自身の内面の変化だけでなく、周囲の人々との関係性にも肯定的な影響を及ぼします。
自他不二の定義
「自他不二」は、仏教において深く掘り下げられた概念の一つであり、自分と他者が本質的には区別されないという教えを表しています。この教義は、個々の存在が孤立したものではなく、全てが相互に繋がっているという仏教の基本的な見方を反映しています。
この教えによれば、私たちが普段認識している「自分」と「他人」という区別は、表面的なものに過ぎず、より深いレベルでは、すべての存在が相互に依存しており、本質的には一つであるとされます。これは、自己中心的な見方から脱却し、他者とのつながりを深く認識することを促します。私たちの行動や考えが、他人や環境に与える影響を深く理解することで、より調和のとれた行動を取ることができるようになります。
また、個人の自己認識だけでなく、コミュニティや社会全体における関係性にも深い影響を及ぼします。自他不二の考え方を受け入れることによって、私たちは他者への共感や理解を深め、偏見や対立を超えた見方を持つことができるようになります。これは、人間関係の質を向上させるだけでなく、私たち自身の精神的な成長にも寄与する重要なステップです。
この概念を理解することは、日々の生活の中で他者との関係を深めるだけでなく、自己の内面に対する洞察をもたらし、より深い自己理解に繋がります。
自他不二の考え方と人間関係
自他不二の哲学は、人間関係において非常に重要な役割を果たします。この考え方は、私たちが他者をどのように認識し、関わるかに深い影響を与え、より健全で充実した関係性の構築に寄与します。
- 共感の深化 自他不二の視点から、私たちは他者の経験や感情を自分のものとして理解することができます。他人の喜びや苦悩を、自分のものとして感じ取ることで、より深い共感と理解を生み出すことができます。この深い共感は、人間関係において信頼と絆を強化し、相互理解を促進します。
- 対立の超越 自他不二の概念を受け入れることにより、私たちは対立や争いを超えた関係性を築くことができます。他人との違いを超えて、共通の人間性を認識することで、互いの違いを尊重し、より和解に向けた姿勢を持つことができます。
- 思いやりと寛容の実践 自分と他者が根本的に一つであるという認識は、思いやりと寛容の心を育みます。私たちが他者の行動や意見に寛容であり、思いやりを持って接することで、より調和の取れた人間関係が築かれます。これにより、人間関係の中でのストレスや不和が減少し、お互いの理解と支持が深まります。
- 相互依存の認識 自他不二の教えは、私たちが相互依存していることを認識する助けとなります。この認識により、私たちは他者との関係において、より責任ある行動を取ることができます。私たちの行動一つ一つが、他者に影響を与えることを理解することで、より考慮深く、丁寧な対人関係を築くことができます。
自他不二の考え方を人間関係に適用することで、私たちはより深い共感、対立の超越、思いやりと寛容、相互依存の認識を通じて、より健全で充実した人間関係を築くことができます。この考え方は、日々の人間関係における対話と理解を深め、より平和で調和のとれた社会を築くための重要な鍵となるでしょう。
日常生活での「自他不二」の実践
「自他不二」の考え方は、具体的には以下のような方法で実践することができます。
- 意識的な聴き方の実践 日常のコミュニケーションにおいて、意識的に他者の話を聴くことは重要です。自他不二の観点から、相手の言葉に耳を傾ける際には、自己の意見や判断を一時的に脇に置き、相手の立場や感情を理解しようとする姿勢が求められます。これにより、相手への深い理解と共感を促進し、より効果的なコミュニケーションを実現します。
- 積極的な共感の表現 自他不二の概念を生活に取り入れる際には、他者への共感を積極的に表現することも大切です。他者の感情や状況に対して、共感的な反応を示すことで、相手の気持ちを尊重し、より強固な関係性を築くことができます。この実践は、相手に対する理解と支持を示し、信頼関係を深めます。
- 寛容さの発展 他者の行動や意見に対する寛容さは、自他不二の哲学において中心的な役割を果たします。他者の違いや欠点を認識しながらも、それを受け入れる態度を持つことで、より調和のとれた人間関係を築くことができます。寛容さを持つことは、他者との関係において柔軟性と理解をもたらし、衝突や誤解を減少させます。
- 日常の状況での応用 自他不二の考え方を日常の様々な状況に適用することで、私たちの人間関係はより円滑になります。職場、家庭、友人関係など、日々の対人関係において、共感、寛容、そして深い理解を心掛けることが重要です。これにより、相互の尊重と理解が深まり、より充実した関係性を築くことが可能になります。
このように、自他不二の概念を日常生活に適用することで、私たちはより調和のとれた人間関係を築くことができます。この実践は、私たちが他者との関わりの中で、より思いやり深く、理解ある存在となることを助けます。

まとめ
自他不二の考え方は、私たちが他者との関係をより深く、より意味あるものにするための鍵となります。他者への共感と理解を深めることで、私たちは相互の信頼と絆を築き、対立や誤解を減らすことができます。この教えに基づいて行動することで、私たちはより寛容で、思いやりのある人間関係を築くことができるのです。
また、自他不二の理解は、私たち自身の内面にも深い影響を与えます。自分と他者が基本的には一つであるという認識は、自己中心的な見方を超えて、より広い視野で世界を見ることを可能にします。これにより、私たちは内面の平和を見つけ、日々の生活においてより穏やかで充実した状態を保つことができるようになります。
自他不二の概念を理解し、日常生活に取り入れることは、私たち一人ひとりがより良い人間関係を築き、内面の充実を実現するための重要なステップです。この教えを実践することで、私たちは他者との関わり合いの中で成長し、より調和のとれた社会の構築に貢献することができるのです。