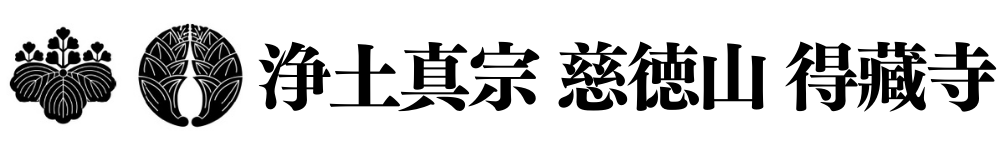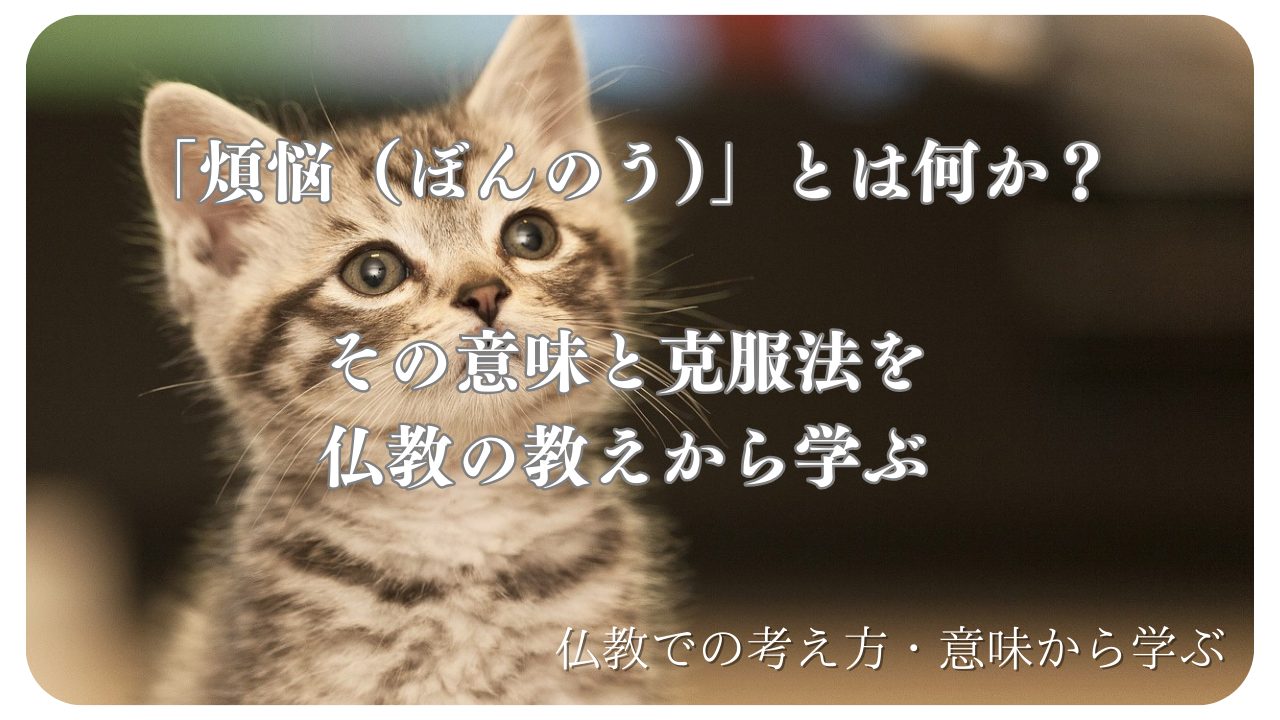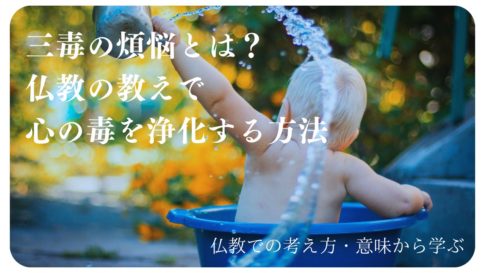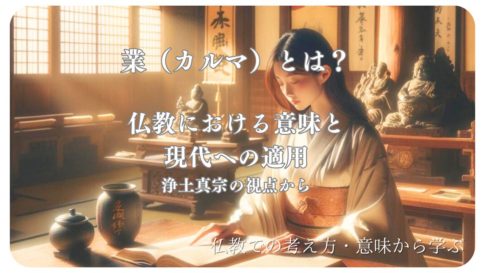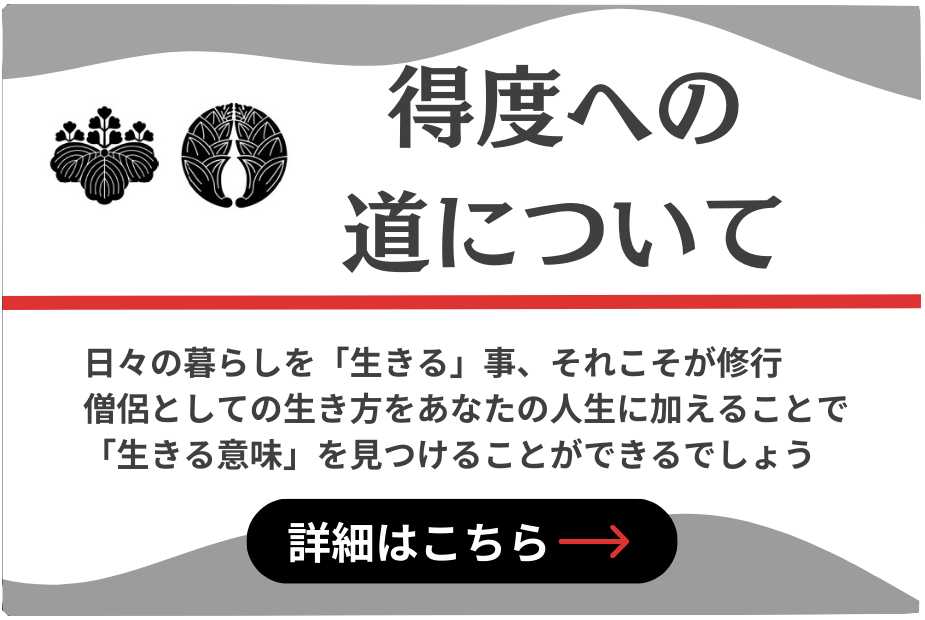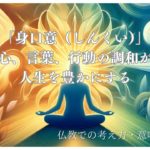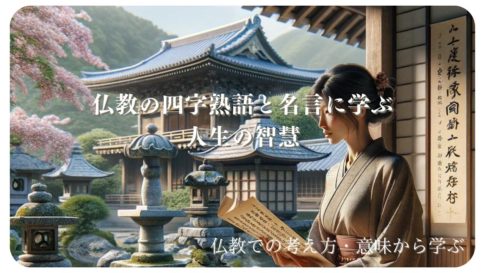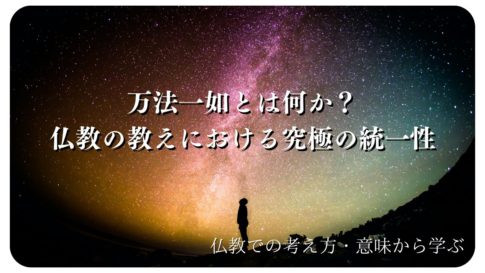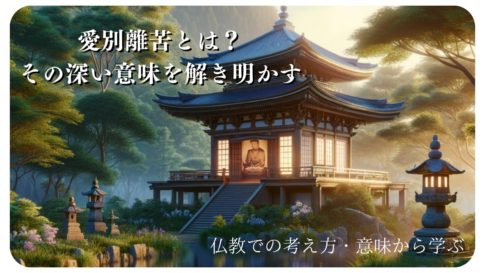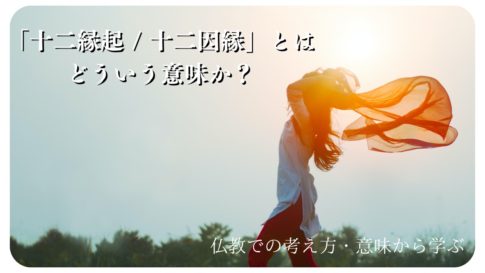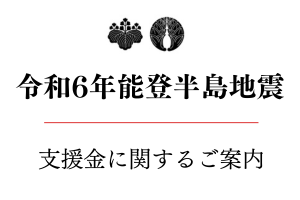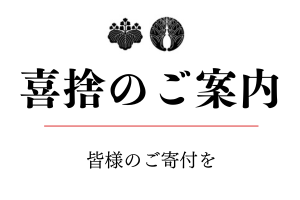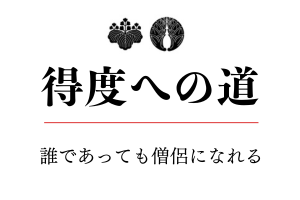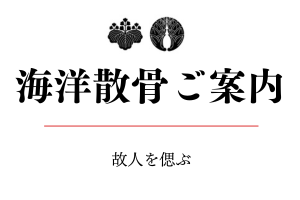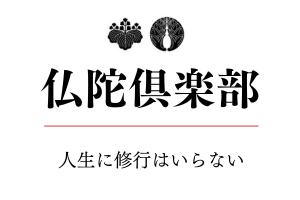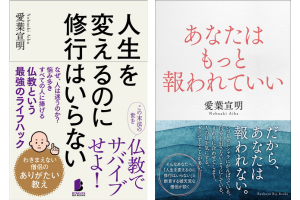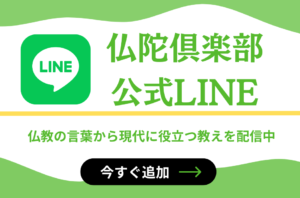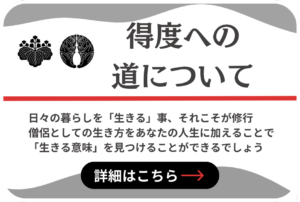目次
私たちの心を乱す「煩悩」
私たち人間の心には、「煩悩(ぼんのう)」と呼ばれる、煩わしい悩みや欲望が存在します。この煩悩は、私たちの心を乱し、苦しみを生む原因となっています。
仏教では、この煩悩を克服し、清らかな心を得ることが、悟りへの道だと説かれています。しかし、現代社会を生きる私たちにとって、煩悩は身近な存在であり、それを完全に取り除くことは容易ではありません。
本記事では、「煩悩」とは何か、その意味と種類について詳しく解説します。また、仏教の教えに基づいて、煩悩を克服するための具体的な方法をご紹介します。
まず、煩悩の定義と、三毒(貪・瞋・癡)について説明します。次に、煩悩の起源であるアラヤ識(アラヤしき)と、カルマ(業)との関係を解説します。さらに、現代社会における煩悩の具体例を示し、心理学の観点からも煩悩について考察します。最後に、仏教の教えに基づく煩悩の克服法と、日常生活に活かすためのヒントをお伝えします。
煩悩とは何か
煩悩の定義と三毒
「煩悩」とは、文字通り「煩わしい悩み」を意味し、私たちの心を乱し、苦しみを生む原因とされています。仏教では、この煩悩を克服し、清らかな心を得ることが、悟りへの道だと説かれています。
煩悩は、通常、三つに分類されます。これを「三毒」と呼びます。
- 貪(とん):欲しいもの、好きなものに対する強い欲望や執着。
- 瞋(しん):嫌いなもの、嫌なものに対する拒絶や憎しみ。
- 癡(ち):真実を見失い、無知でいる状態。自分の欲望や憎しみに囚われている状態。
この三毒は、私たちの心を惑わし、苦しみを生み出す根源となっています。
煩悩の起源 – アラヤ識とカルマ
では、煩悩はどこから生まれるのでしょうか?
仏教では、煩悩の根源は、私たちの無意識の深い部分、アラヤ識(アラヤしき)にあると説かれています。
アラヤ識とは、私たちの過去の行動や経験が蓄積された無意識の領域です。このアラヤ識が、私たちの現在の思考や行動に影響を与えるのです。過去の経験から生まれた執着や拒絶が、煩悩の種となっているのです。
また、アラヤ識には、過去世における行動(カルマ)も蓄積されていると考えられています。このカルマが、現在の私たちの運命を左右するとされています。
つまり、煩悩は、私たちの過去の経験やカルマから生まれ、私たちの思考や行動に影響を与えているのです。

煩悩を現代の言葉で解釈する
「煩悩」は仏教の概念ですが、現代の言葉で言い換えると、「マイナスの感情や思考」、「ネガティブなエネルギー」、「心のブロック」などと表現できるでしょう。
例えば、貪(とん)は「過度な欲望」や「執着」、瞋(しん)は「憎しみ」や「拒絶」、癡(ち)は「無知」や「誤解」などと言い換えることができます。
これらの煩悩は、私たちの日常生活において、ストレスや不安、不満などの形で現れます。
現代社会での煩悩の具体例
現代社会において、煩悩は様々な形で現れます。例えば、以下のような状況が考えられます。
- SNSで他人と自分を比較し、劣等感を感じる
- 物質的なものに過度に執着し、満足できない
- 他人に対して妬みや恨みを抱き、人間関係がうまくいかない
- 自分を過大評価、または過小評価し、自信を失う
これらは、現代社会における煩悩の具体的な例です。私たちは日々、このような煩悩に悩まされているのです。
心理学の観点から見た煩悩
心理学の観点から見ると、煩悩は、私たちの心の健康に悪影響を与える要因と言えます。
例えば、貪(とん)は「過度な欲望」や「依存」につながり、瞋(しん)は「怒りのコントロールができない」、「過度なストレス」につながります。また、癡(ち)は「現実逃避」や「認知の歪み」につながります。
これらの煩悩は、心の健康を損ない、精神的な疾患を引き起こす可能性があります。したがって、煩悩を克服し、心の健康を保つことは、現代人にとって非常に重要なテーマなのです。

煩悩の克服法
仏教的な煩悩の克服法
仏教では、煩悩を克服するために、以下の方法が推奨されています。
- 自覚:まず、自分の煩悩に気づくことが重要です。自分の心の動きに注意を払い、煩悩に気づくことから始めます。
- 受け入れ:次に、自分の煩悩を受け入れます。煩悩に抵抗することなく、その存在を認めます。
- 解放:最後に、煩悩を手放します。煩悩に囚われず、自分を解放します。
この過程を通じて、私たちは煩悩を克服し、清らかな心を得ることができるのです。
日常生活での煩悩の管理法
日常生活で煩悩を管理するための具体的な方法には、以下のようなものがあります。
- 瞑想:日常的に瞑想を行うことで、心を鎮め、煩悩に対する自覚を高めることができます。
- ポジティブな習慣:ポジティブな習慣を形成することで、煩悩の影響を減らすことができます。例えば、運動、健康的な食事、十分な睡眠などです。
- 感謝の実践:感謝の気持ちを持つことで、ポジティブな思考を促し、煩悩を和らげることができます。
これらの方法を日常生活に取り入れることで、煩悩を管理し、心の平安を得ることができるのです。
おわりに
煩悩を理解し、日常に活かす
煩悩は、私たちの心の平安と幸福に大きな影響を与えます。それは、私たちの思考、感情、そして行動を動かす力なのです。
だからこそ、煩悩を理解し、それを管理することが、心の平安を得るための重要なステップとなります。
煩悩を克服することは、日常生活に多くのポジティブな影響をもたらします。ストレスや不安を減らし、人間関係を向上させ、自分自身をより深く理解することができるのです。
私たち一人一人が、自分の煩悩に向き合い、それを管理していくことが大切です。仏教の教えに学びながら、日々の生活の中で実践していくことが、煩悩を克服する鍵となるでしょう。
皆さまも、ぜひ自分の心の中にある煩悩に目を向けてみてください。そして、仏教の教えを参考にしながら、煩悩と向き合い、それを管理していく方法を探ってみてください。
きっと、心の平安と幸福への道が開かれるはずです。一緒に、煩悩を克服し、清らかな心を目指していきましょう。
南無阿弥陀仏