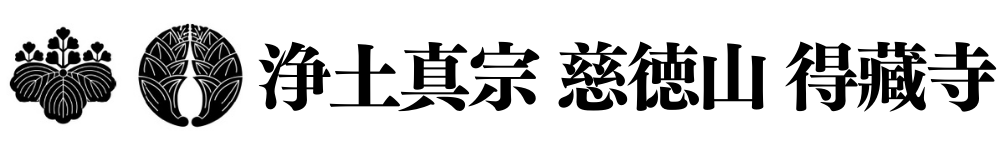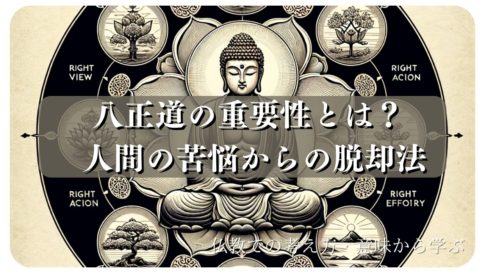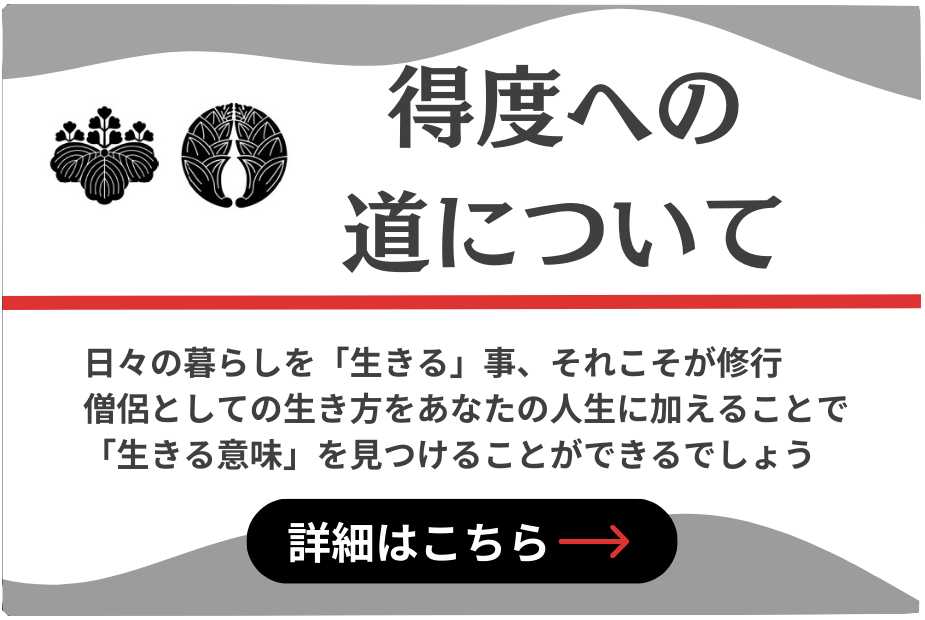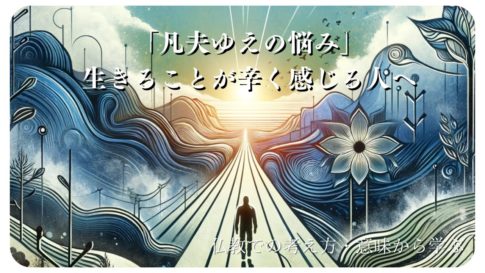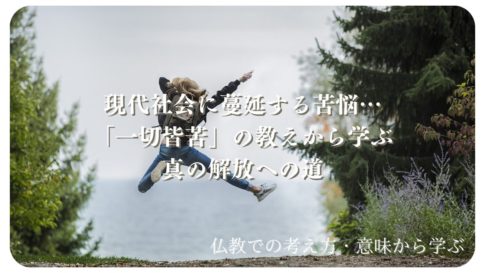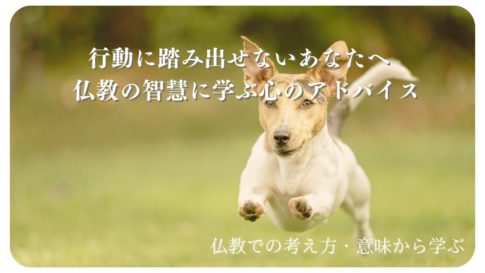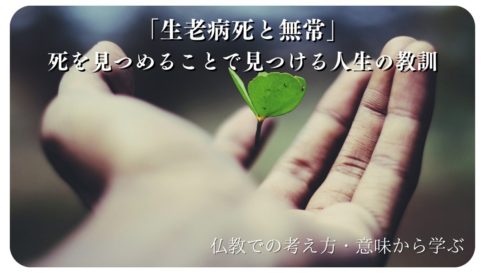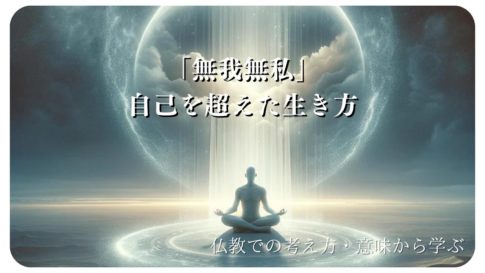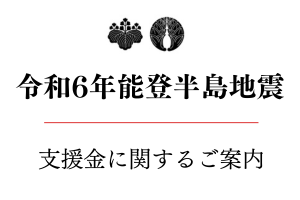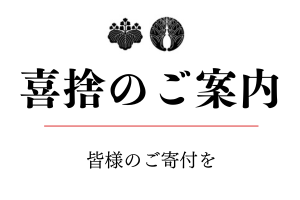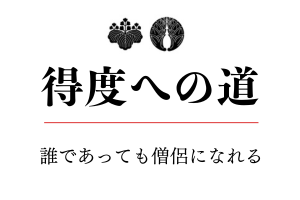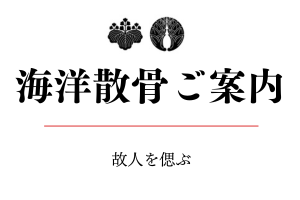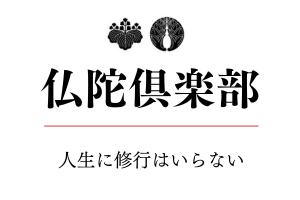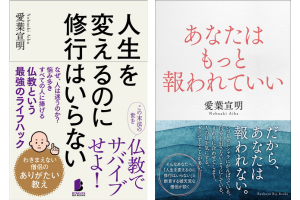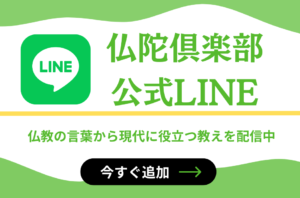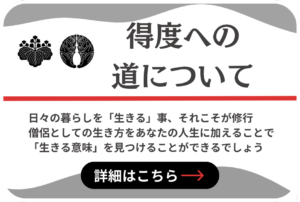目次
仏教の基本的な教えとしての「中道」
「中道」は、仏教の基本的な教えのひとつです。これは、極端な自己抑制と放縦な生活のどちらも避け、均衡と調和のとれた生き方をするという教えです。
ゴータマ・シッダールタ(後の仏陀)は、自己抑制も過度な享楽も避け、その中間に位置する道を実践することで、真の覚りを得たとされています。
この「中道」の概念は、八正道とも密接に関連しており、仏教徒の生活と修行の基本的な指針となっています。
現代における「中道」の意義
現代社会は、情報過多であり、多忙かつストレスフルな場面が多く存在します。このような環境下で、「中道」の教えは非常に重要な意義を持ちます。
それは、極端な行動や思考を避け、心のバランスを保ち、健やかな精神状態を維持するための方法として、現代人にとって有効な指針となるからです。
また、「中道」の実践は、持続可能な生活のあり方を形作り、自己と他者、そして環境との調和を促す重要な要素とも言えます。
「中道」の本来の意味
古典的な仏教文献では、「中道」は極端な自己抑制と放縦な生活のどちらも避け、中庸の道を歩むとされています。
具体的には、初期の仏教文献であるパーリ語経典において、中道は「八正道」の一部として説かれています。
八正道とは、正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定という8つの要素から成り立っており、これを実践することによって苦しみから解放され、覚りを開くとされています。
どういう意味か?
「中道」とは、文字通り「中央の道」を意味し、極端な行動や思考を避け、均衡と調和を保つ生き方を指します。
これは、過度な自己抑制や苦行を行うことなく、また、放縦や過度な欲望に走ることなく、心地よいバランスを保ちながら生きることを意味します。
例えば、食事においても極端な断食や過食を避け、体に必要な栄養を適切に摂るよう心がけるといった具体的な生活の中での実践も含まれます。

現代の言葉に「中道」を置き換えると?
「中道」は現代の言葉で表現すると「バランスの取れた生き方」や「調和のとれた存在」などといえます。
近年の心理学では、自己の健康を維持するための「セルフケア」や「マインドフルネス」といった概念も、「中道」の教えと共鳴する点が多く見受けられます。
これらは、極端なストレスや自己抑制から自身を解放し、より健やかで豊かな心の状態を目指すという、同じ目的を共有していると言えます。
現代の心理学や哲学における「中道」の解釈
現代の心理学においては、例えば「認知行動療法」に代表される治療法が、「中道」の概念と重なる部分を持っています。
認知行動療法は、極端な否定的な思考を是正し、より現実的かつポジティブな思考へと導く方法を教えるものです。
これは、中道の教えが目指す、極端な思考や行動を避け、均衡を保つ生き方と同じ考え方を反映しています。
また、西洋哲学における「黄金の中庸」も、極端を避けることの重要性を説く点で「中道」と共通する思想です。
シチュエーション別「中道」の実践
日常生活での「中道」の例
日常生活における「中道」の実践例としては、食事、運動、睡眠などの基本的な生活習慣のバランスが挙げられます。
例えば、食事では極端な食事制限や過食を避け、栄養バランスを考えた適切な量を摂ること。
運動においても、過度なトレーニングではなく、継続可能な適切な運動量を心がけることが、「中道」の生き方を具現化する一例と言えます。
ビジネスやキャリアにおける「中道」
職場における「中道」の実践は、極端な労働と自己犠牲を避け、自身の健康と仕事の品質を両立させる働き方を目指すことにつながります。
例えば、極端な残業を避け、効率的な時間管理を行うことで、仕事の質を高めながら自身の健康とプライベートの時間も大切にすることが可能です。
人間関係や健康面での「中道」
人間関係における「中道」は、他人との関係で極端な依存もしくは過度な距離感を避け、健全な関係性を築くことを指します。
例えば、パートナーや友人との関係で、過度な依存をせず、相手の自由を尊重しつつ、必要な時にはしっかりとサポートを行うバランスが大切です。
健康面では、極端なダイエットや運動を避け、継続的な健康管理を心がけることが重要です。

「中道」の実践方法: バランスを取るための習慣やテクニック
「中道」を日常に活かすためには、自己認識と自己調整が重要です。
例えば、一日のスケジュールを計画する際に、労働と休息のバランスを意識的に取ること。
また、感情のコントロール法として、怒りや悲しみが高ぶった時に深呼吸をするなどのシンプルな方法も効果的です。
逆境時における「中道」の活用: 考え方や行動のヒント
逆境時に「中道」を活用するためには、極端な責任の所在や自己非難を避け、冷静に状況を分析することが大切です。
例えば、失敗した際に全責任を自分に押し付けず、状況を客観的に分析し、次の行動を冷静に計画することが重要です。
極端な思考や行動の危険性
現代社会は情報過多であり、その影響で極端な思考に陥りやすい傾向があります。
例えば、SNSでの比較や極端なダイエットへの挑戦など、自己の価値を外部の評価で測る傾向が強まっています。
これらの極端な行動は、精神的なストレスを増大させ、健康を損なう可能性があるため、その危険性を知ることが重要です。
「中道」を通じて極端な行動をコントロールする方法
極端な行動をコントロールするために、「中道」の原則を思い出し、自分自身との対話を重視することが大切です。
例えば、自分が何を求めているのか、本当に重要なことは何かを明確にし、それを基に行動を整えることが大切です。
瞑想や自己啓発の書籍を読むことも、自分自身と向き合い、中道を実践する手段となる場合があります。

「中道」の心理的・健康的な効果
自己肯定感と「中道」
「中道」は、極端な感情や反応を避け、穏やかでバランスの取れた精神状態を保つことを目指します。
これにより、ストレスや過度な心配からくる精神的な負担が軽減され、心の安定がもたらされます。
例えば、完璧を求めすぎず、自分自身を受け入れることで、自己肯定感が向上し、より健全な精神状態になります。
「中道」の生き方がもたらす健康面での利点
「中道」の生き方は、心だけでなく、体の健康にも寄与します。
バランスの取れた食生活や適度な運動は、肥満や生活習慣病を防ぎます。
また、「中道」の精神は、過度なストレスを軽減し、それによる健康への悪影響を最小限に抑える助けにもなります。
「中道」を理解し、生き方に取り入れる重要性
現代人としての「中道」の受け止め方
現代社会は速度が重視され、極端な価値観が多く存在します。
その中で「中道」は、バランスと調和の重要性を再認識させ、心と体の健康を保つための鍵となります。
現代人は、情報過多の中での判断や、多様な価値観を受け入れる柔軟性を持つために「中道」の思考が重要であると理解する必要があります。
今後の生活での「中道」の活用方法
「中道」を日常生活に取り入れるためには、自己認識と自己調整が大切です。
例えば、日々の選択をする際に、極端な選択肢ではなく、バランスを重視した選択を心がけることが大切です。
また、自分の感情や状態を常に観察し、必要な調整を行う習慣を持つことも重要です。