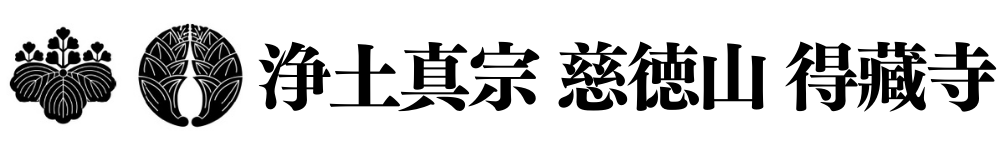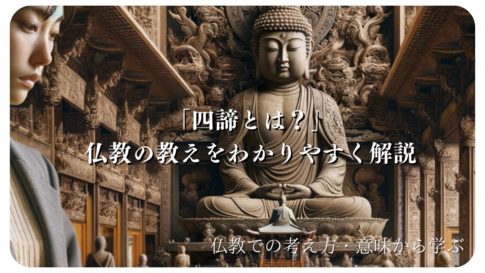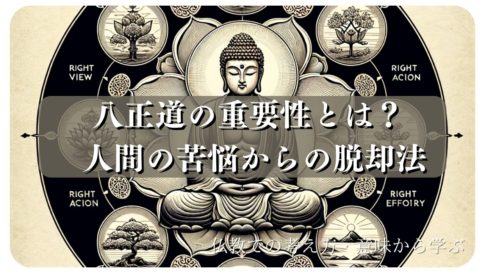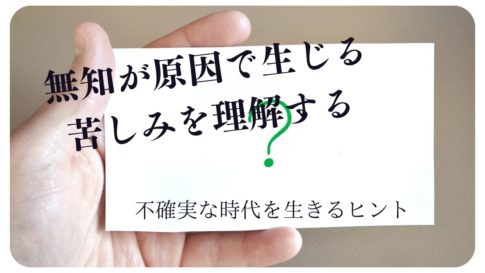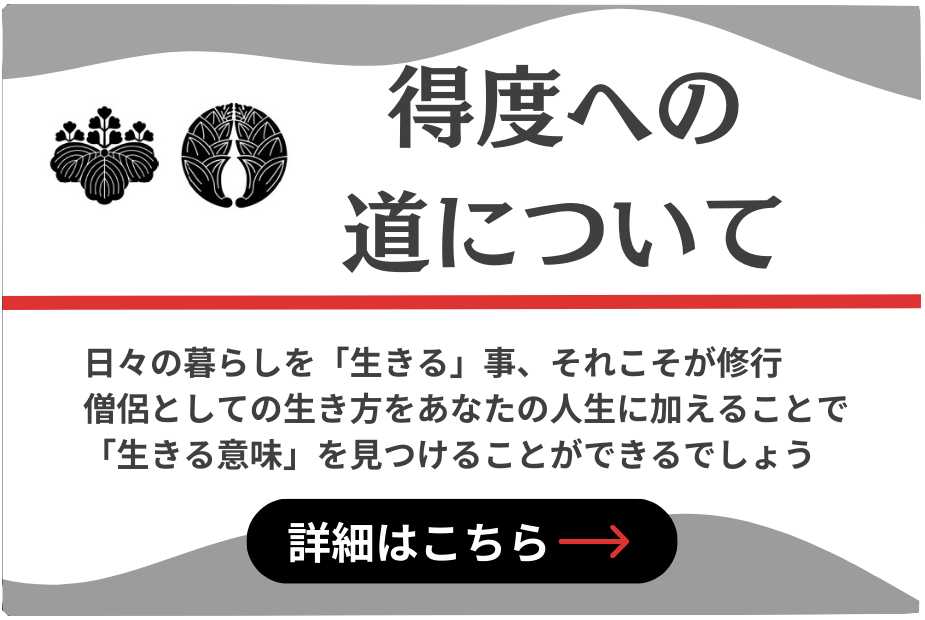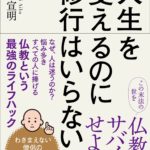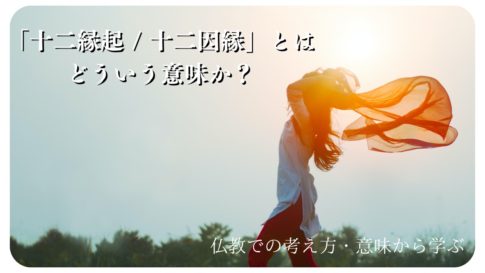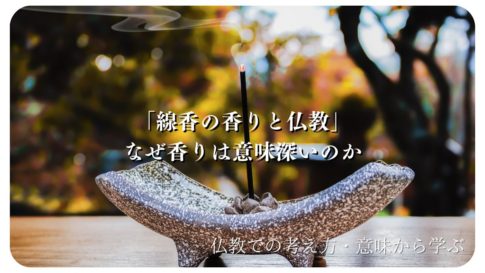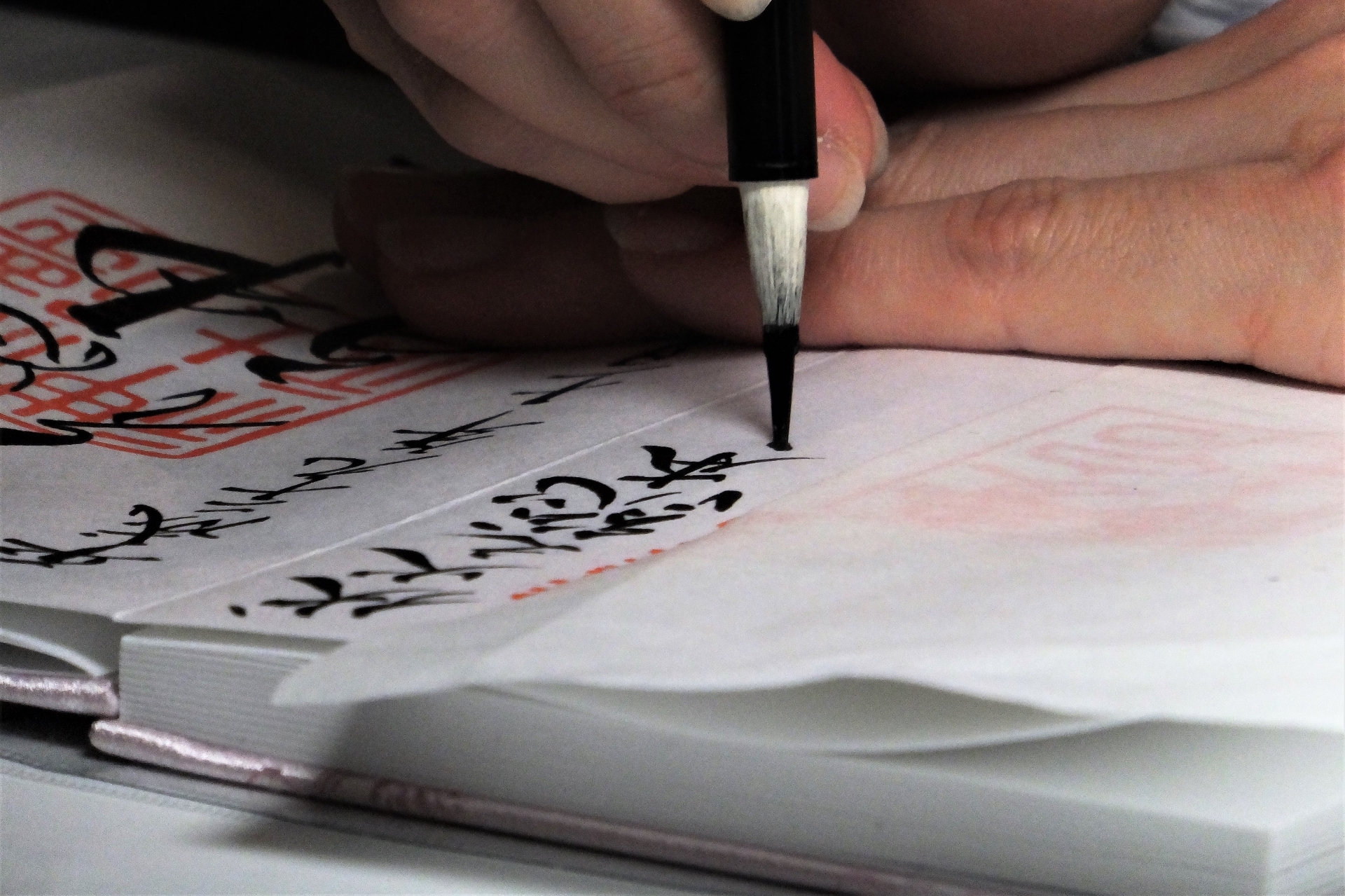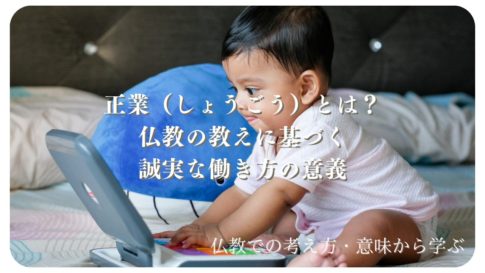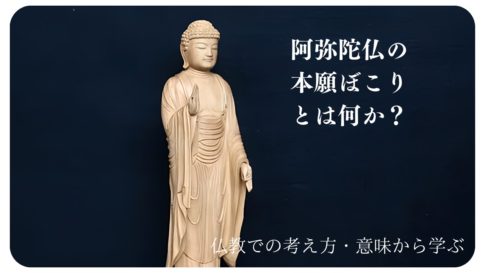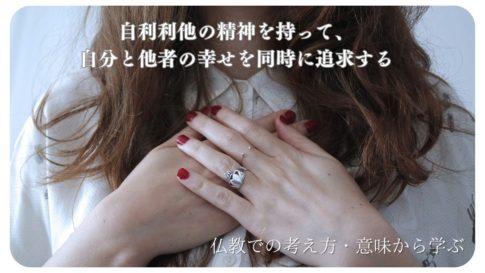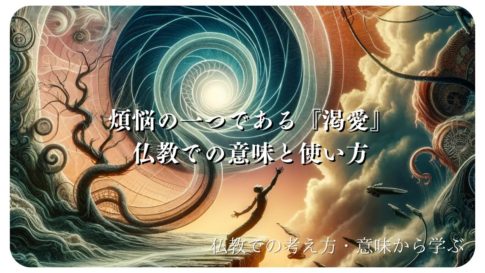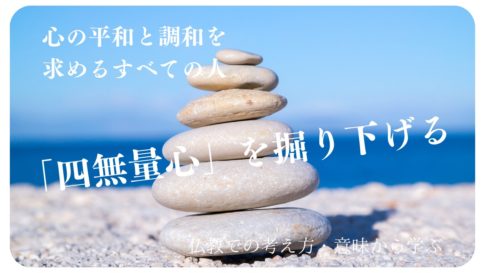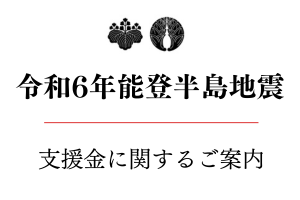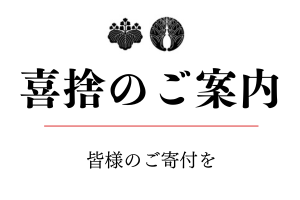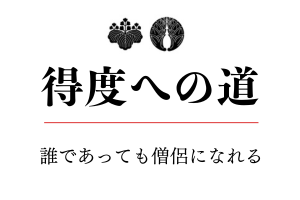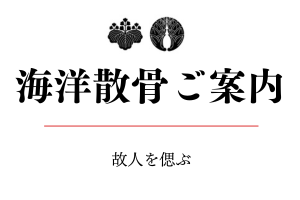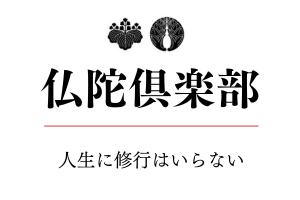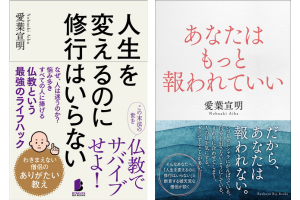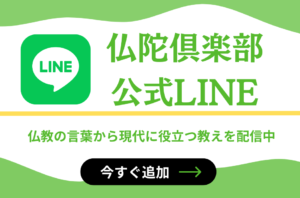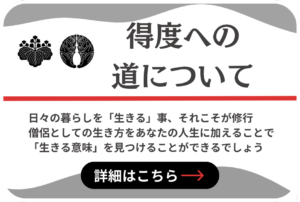「四苦八苦」の誤解と真意
四苦八苦とは何か
最初に、私たちは「四苦八苦」という言葉の基本的な理解から始めることが重要です。
このフレーズは日本の日常会話でよく使われ、大きな困難や苦しみを経験していることを表します。
しかし、この表現の本来の意味は、仏教の教えに深く根ざしており、その真の意味を理解することは私たちの人生の苦しみを軽減するための第一歩となります。
「四苦八苦」の誤用と普及について
「四苦八苦」の言葉は多くの場合、誤って解釈され、使われています。
私たちが困難な状況や困惑しているときによく使うこのフレーズは、実際には仏教の教えである「四苦」(生、老、病、死)と「八苦」(愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五陰盛苦)を指しています。
しかし、日常的に使われる際には、その深い意味は忘れ去られ、一般的に大きな困難を経験している様子を表すためのフレーズとなってしまっています。
「四苦八苦」の真の意味: 仏教的視点
本当の「四苦八苦」の意味を理解するためには、仏教の教えに立ち返る必要があります。
四苦は、生まれる苦しみ(生苦)、老いる苦しみ(老苦)、病む苦しみ(病苦)、死ぬ苦しみ(死苦)を意味します。
さらに、これらを具体化したのが八苦で、人間が避けられない8つの苦しみを指します。
これは、愛するものとの別離(愛別離苦)、嫌いなものとの出会い(怨憎会苦)、望むものが手に入らないこと(求不得苦)、五蘊(身と心)の苦しみ(五陰盛苦)です。
現代的な「四苦八苦」の具体的シチュエーション例
例えば、仕事のプレッシャーによりストレスを感じている(求不得苦)、恋人との別離に苦しんでいる(愛別離苦)、親の老いや病気(老苦・病苦)など、私たちは日常生活で四苦八苦に直面しています。
また、新型コロナウイルスのパンデミックは全世界で「四苦八苦」の状況を引き起こし、人々が生死(生苦・死苦)や社会的孤立(怨憎会苦)といった深刻な苦しみを経験しました。
四苦八苦の理解はあなたの非ではない
多くの人が「四苦八苦」の言葉の真の意味を理解していないのは、それがあまりにも広く誤用されているためです。
しかし、それはあなたの非ではありません。むしろ、これはあなたがこの古い言葉の本当の意味を学び、それがあなた自身の人生や他人の苦しみにどのように関連しているかを理解する絶好の機会です。
この理解があなたの人生の視点を変え、新たな方向へと導くかもしれません。

人生の苦しみから解放される方法: 仏教の教え
仏教の基本原則: 苦の原因と解消方法
仏教の基本的な教えの一つに、「四諦(したい)」があります。
これは苦諦(くたい:人生は苦である)、集諦(しゅうたい:苦の原因は無知と欲望)、滅諦(めったい:苦を絶つ方法)、道諦(どうたい:苦から解放される道)という四つの真理を表しています。
この中でも、苦の原因と解消方法を理解することが、人生の苦しみを乗り越える一助となります。
苦の原因は、自身の無知と欲望にあると仏教は教えています。そして、その苦しみを解消するための道は、「八正道」として示されています。
四苦八苦からの解放: 八正道
仏教で説かれる「八正道」とは、
- 真実に向かって正しく見る(正見)
- 正しい思考を持つ(正思惟)
- 正しく言葉を使う(正語)
- 正しい行動をする(正業)
- 正しい生業を選ぶ(正命)
- 正しい努力をする(正精進)
- 正しいマインドフルネスを持つ(正念)
- 正しい集中力を持つ(正定)
という8つの道徳的な行動です。
これらは、人間が生きていく中で直面する「四苦八苦」を克服し、より良い生き方を模索するための具体的な指針となります。
八正道については、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
四苦八苦の現代的な解釈と対策
現代社会でも、「四苦八苦」は私たちが日々直面するリアルな問題を象徴しています。
一方で、古代の仏教の教えが現代の苦しみに対してどのように適用され得るかという課題が存在します。
しかし、重要なことは、四苦八苦とは、単に困難や問題を示す抽象的な概念ではなく、具体的な生活の中での挑戦や困難、そしてそれらを乗り越えるための方法論を指しているということです。
例えば、欲望のコントロール、適切な生業の選択、心の平穏を維持するためのマインドフルネスなど、仏教の教えは現代人が直面する問題に対する具体的な解決策を提供します。
それらを日々の生活に活かしていくことで、四苦八苦を乗り越え、人生をより良いものにしていくことが可能です。

仏教の教えを日常生活にどのように適用するか
悩みの源を見つける: 無知から覚醒へ
人生の悩みや問題は多くの場合、我々が自分自身や世界についての真実を見失っている結果です。
これは仏教でいうところの「無知」に該当します。
そのため、四苦八苦からの脱出の第一歩は、自分の無知を認識し、それを排除することです。
無知とは、自分自身や世界がどのように機能しているか、何が本当に大切なのかを理解していない状態を指します。
この認識を深め、真実を追求することで、我々は苦しみの根源を見つけ、解消するための道筋を描くことが可能になります。
無知に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
苦しみから解放する行動: 八正道の具体的な適用
四苦八苦から解放されるためには、「八正道」を日常生活に具体的に適用することが重要です。
例えば、
「正見」は自己と他者、そして世界に対する明確な理解を持つこと。
「正思惟」は偏見や先入観を排除した公正な思考を行うこと。
「正語」は優しく、真実を伝え、他人を傷つけない言葉を使うこと。
を指します。
これらの行動は、私たちが人生の苦しみを和らげ、内面的な平和を得るための具体的な方法となります。
四苦八苦を乗り越える心構え
四苦八苦から解放されるための最終的なステップは、自己改革と心の変革です。
我々が日常生活で直面する多くの問題は、我々自身の思考や行動のパターンに起因しています。
したがって、自分自身の行動や思考を変えることで、人生の苦しみを克服することが可能です。
また、一貫した正義、善良さ、思いやりといった価値観を持つことで、人生の困難を前向きに捉え、乗り越えることができます。
四苦八苦を乗り越えるためには、自己改革と心の変革が欠かせません。
これは、人生の困難を克服し、より良い人生を創造するための究極的な武器となるでしょう。
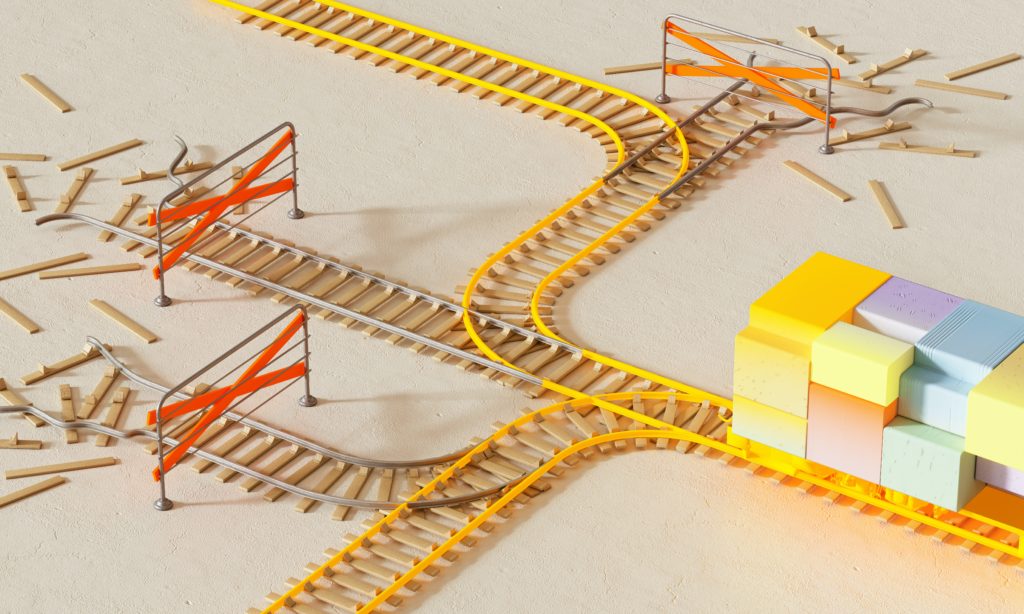
「四苦八苦」を乗り越えるための具体的なステップ
あなた自身の「四苦八苦」を理解する
まず第一に、自分が何に苦しんでいるのか、何が原因で「四苦八苦」を経験しているのかを理解することが重要です。
自己分析や自己反省によって、自分の問題点や困難を具体的に把握しましょう。
無知、欲望、嫉妬、怒りなど、これらは全て人生の苦しみを生む原因です。
自分自身の内面を深く見つめ、これらのネガティブな感情や欲望がどのように影響を与えているのかを理解することが、四苦八苦を乗り越える第一歩となります。
日々の生活に仏教の教えを取り入れる方法
次に、仏教の教えを日常生活に取り入れる具体的な方法について考えてみましょう。
例えば、マインドフルネス瞑想は、自分自身の心と身体を深く理解するための有効な手段です。
これは、自分の感情や思考、身体の感覚に対して意識的であることを練習する方法で、心の平穏を得るための有効な道具となります。
また、「八正道」の教えを日常生活に取り入れることも重要です。
言葉遣い、行動、職業の選択など、日常生活のあらゆる面で「八正道」を体現することで、自己改善と内面的な平和を追求することが可能になります。
道徳的な生活を送るための具体的なアドバイス
道徳的な生活を送ることは、「四苦八苦」を乗り越えるための大切な要素です。
そのための具体的なアドバイスとしては、以下のようなことが挙げられます。
まず、他人に対する思いやりと共感を持つこと、自分自身と他人を尊重すること、そして正直で誠実な態度を持つことです。
また、贅沢や過度な物欲を避け、質素な生活を送ることも重要です。
これらは全て、人間が持つ欲望をコントロールし、内面的な平和を得るための方法となります。
修行は必要ない: 人生を変えるための新たな視点
最後に、四苦八苦を乗り越えるためには必ずしも修行や厳格な宗教的な生活を送る必要はありません。
大切なのは、自分自身の思考や行動、そして日々の生活の中での選択を見つめ直すことです。
これは、あなた自身が自分の人生をコントロールし、幸せと満足感を追求するための新たな視点を提供します。
四苦八苦を乗り越えるための旅は、自己理解と自己改革から始まります。
そして、それは山での厳しい修行や禁欲生活ではなく、日常生活の中での小さな一歩から始まるのです。
この記事は、仏教の教えを日常生活にどのように適用できるかを理解し、人生に苦しみを感じている人々に対して新たな視点を提供することを目指しています。
この記事があなたの日々の苦しみを少しでも和らげる手助けになることを願っています。