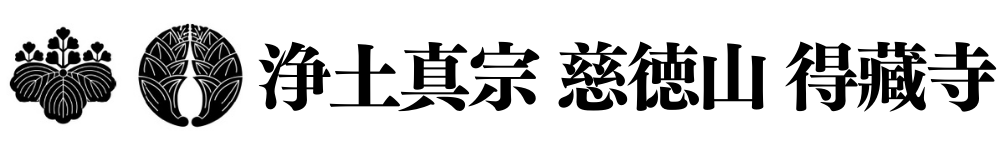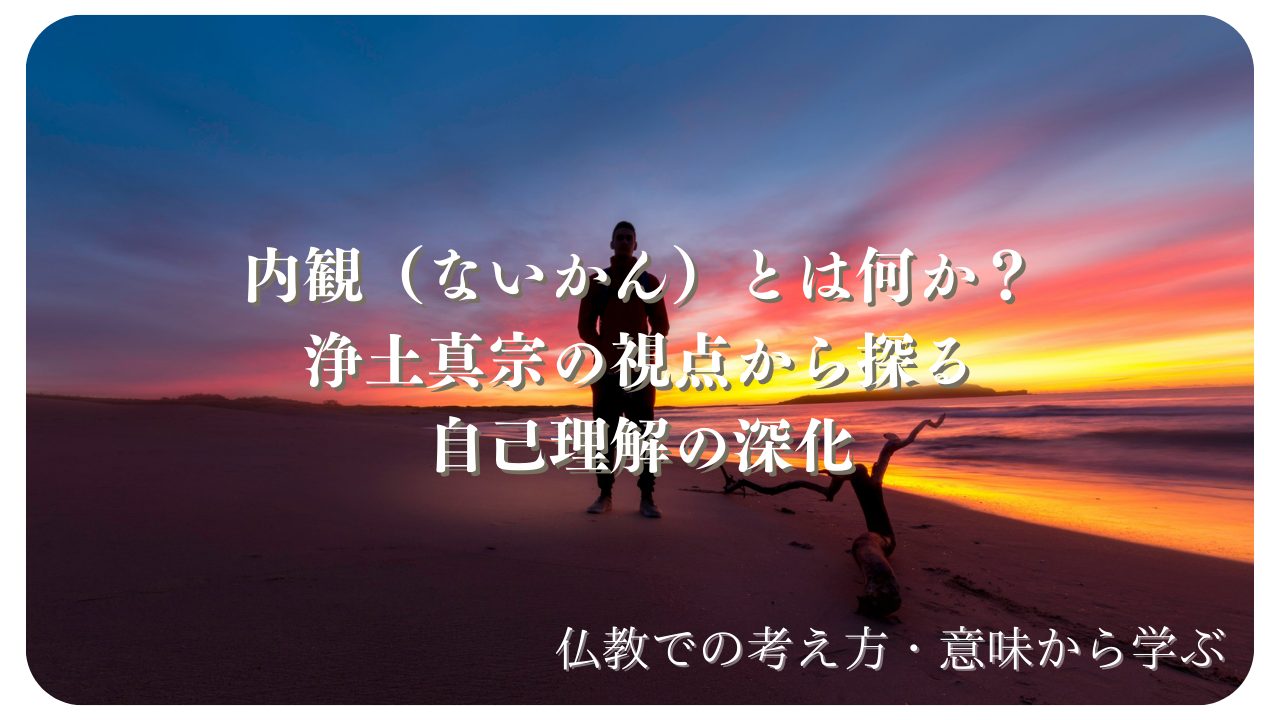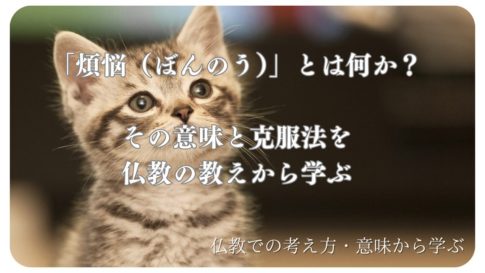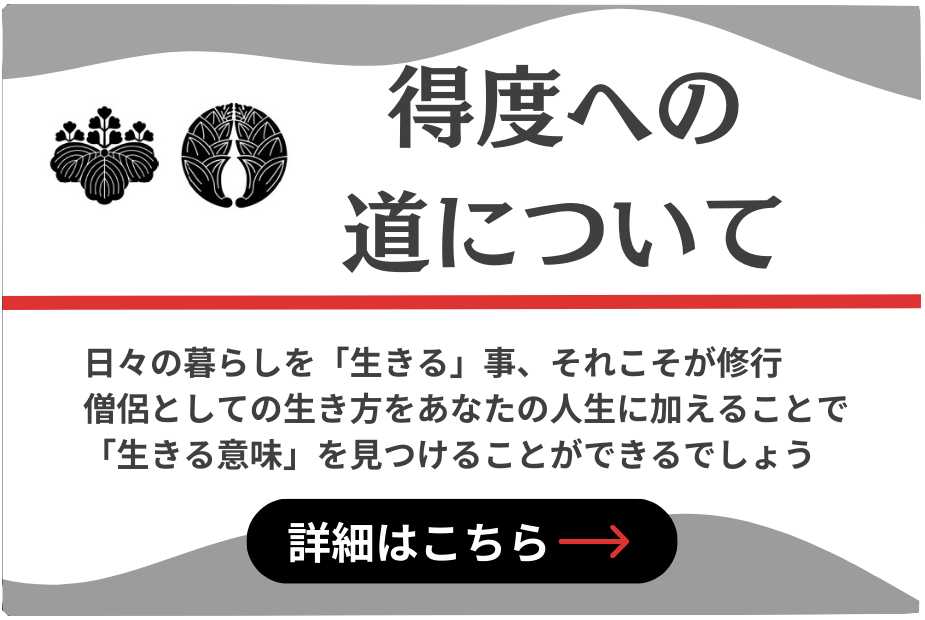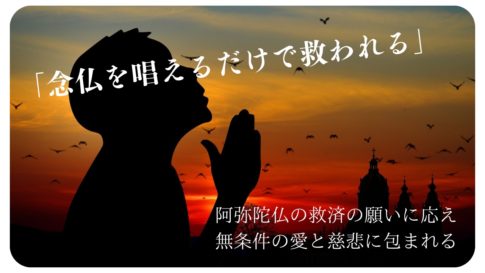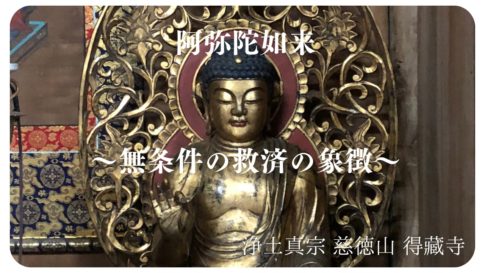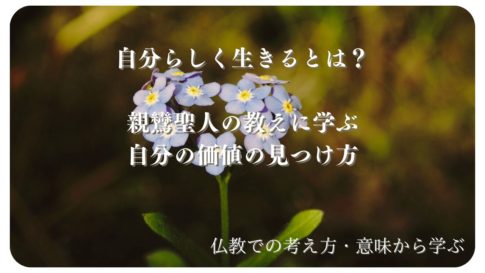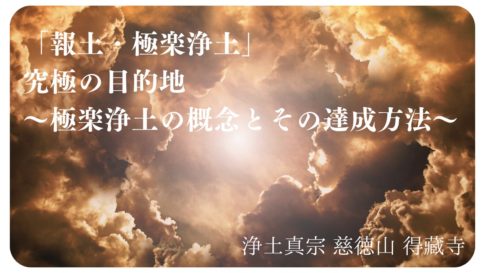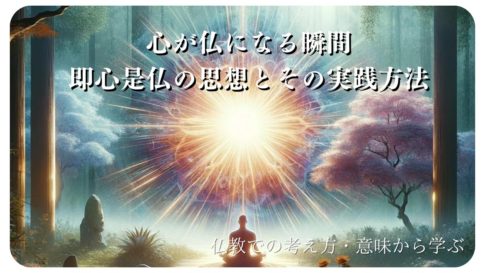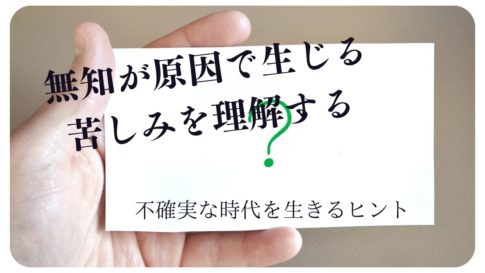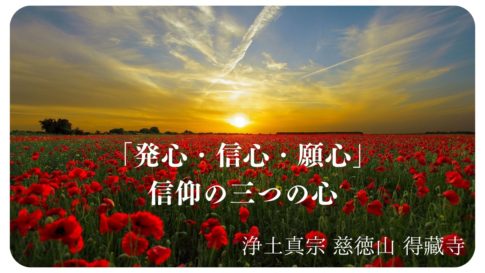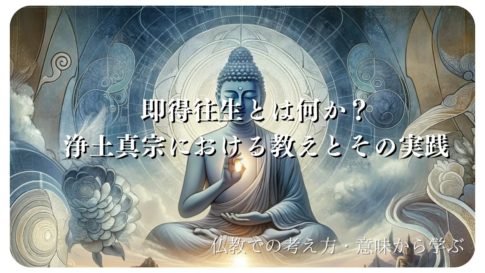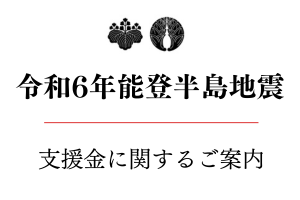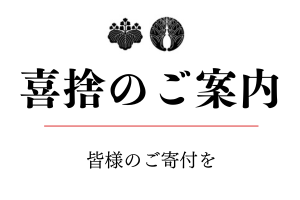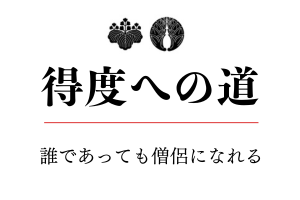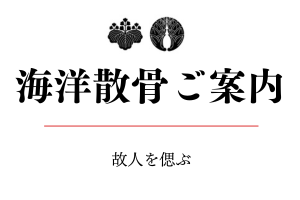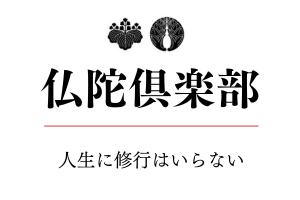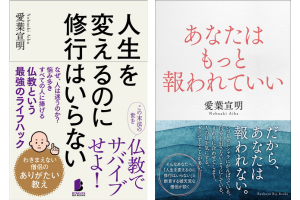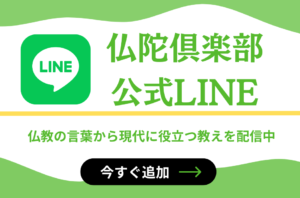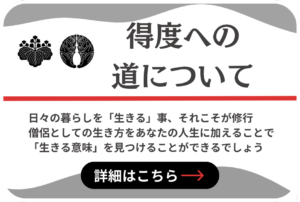本記事では、仏教用語の一つである「内観」について、浄土真宗の視点を交えながらお話ししたいと思います。
内観は、自分自身の内面を深く見つめ、自己理解を深めるための重要な実践です。現代社会を生きる私たちにとって、内観がどのような意味を持つのか、一緒に考えていきましょう。
内観の意味と目的
内観とは、文字通り「内面を観察する」ことを意味します。
具体的には、自分の感情、思考、行動パターンなどを客観的に観察し、自己理解を深めることを目的とした実践です。仏教では、内観を通じて自分自身の真の姿を見つめることが、悟りへの道につながると説かれています。
内観は、自分自身と向き合うことで、自分の長所や短所、癖やパターンに気づくことができます。これは、自己成長や人間関係の改善にも大きな影響を与えます。内観を通じて自分自身を深く理解することは、他者への理解と共感にもつながるのです。
浄土真宗における内観の位置づけ
浄土真宗では、阿弥陀仏の慈悲によって救われるという「他力本願」の教えが中心となりますが、同時に自力の実践も重視されています。内観は、まさにその自力の実践の一つと言えるでしょう。
親鸞聖人は、「自己を知る」ことの大切さを説いています。自分自身の煩悩や無明に気づくことは、阿弥陀仏の慈悲をより深く理解することにつながると言えます。内観を通じて自己の限界を知ることで、私たちは他力への信頼をさらに深めることができるのです。
内観の実践方法
内観の実践には、様々な方法がありますが、ここでは基本的なステップをご紹介しましょう。
- 静かな場所で座り、深呼吸をしながら心を落ち着けます。
- 自分の感情や思考を、あるがままに観察します。良い悪いの判断はせず、ただ見つめます。
- 観察した感情や思考の背景にある、自分の価値観やこだわりに気づきます。
- 自分の特徴やパターンを客観的に理解し、受け入れます。
大切なのは、自分を責めたり否定したりしないことです。あくまでも中立的な立場から、自分自身を見つめる姿勢を保ちましょう。
日常生活への内観の活用
内観は、座禅などの特別な時間だけでなく、日常生活の中でも実践することができます。例えば、人間関係で悩んだとき、自分の感情や反応を内観することで、新たな気づきが得られるかもしれません。
また、日々の生活の中で、自分の言動を振り返る習慣を持つことも大切です。「今日はどのような感情を感じただろう?」「自分の行動は相手にどう影響したか?」といった問いを自分に投げかけてみましょう。
おわりに
内観は、自分自身と向き合い、自己理解を深めるための強力なツールです。浄土真宗の教えに照らし合わせると、内観は自力の実践であると同時に、他力への信頼を深める営みでもあるのです。
日常生活の中で内観を実践することで、私たちは自分自身だけでなく、他者への理解と共感をも深めることができるでしょう。そうした歩みの先に、より豊かな人生が開かれているに違いありません。