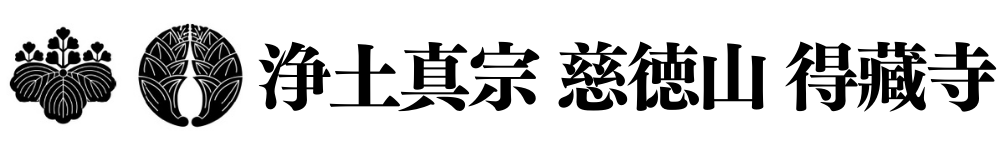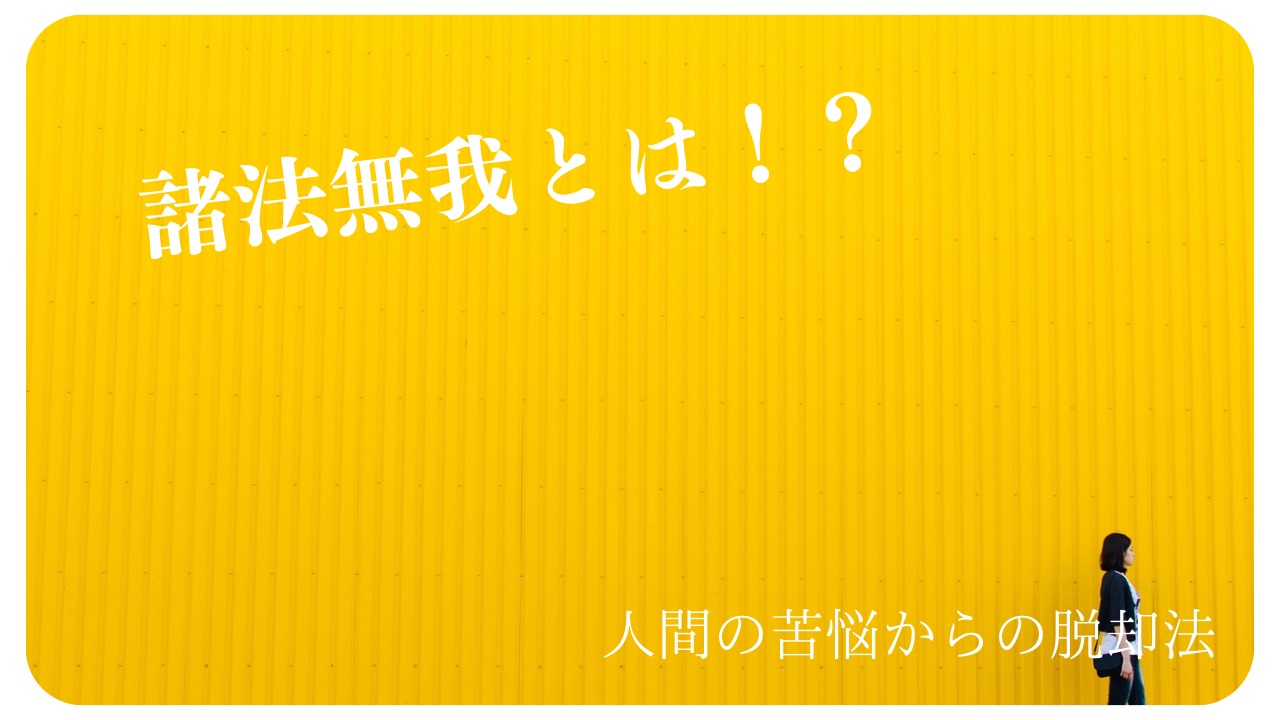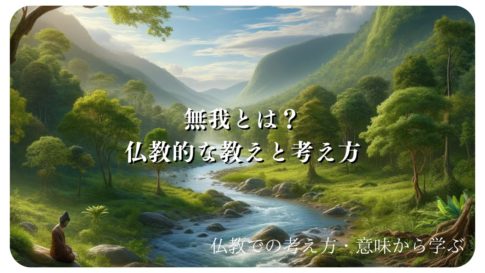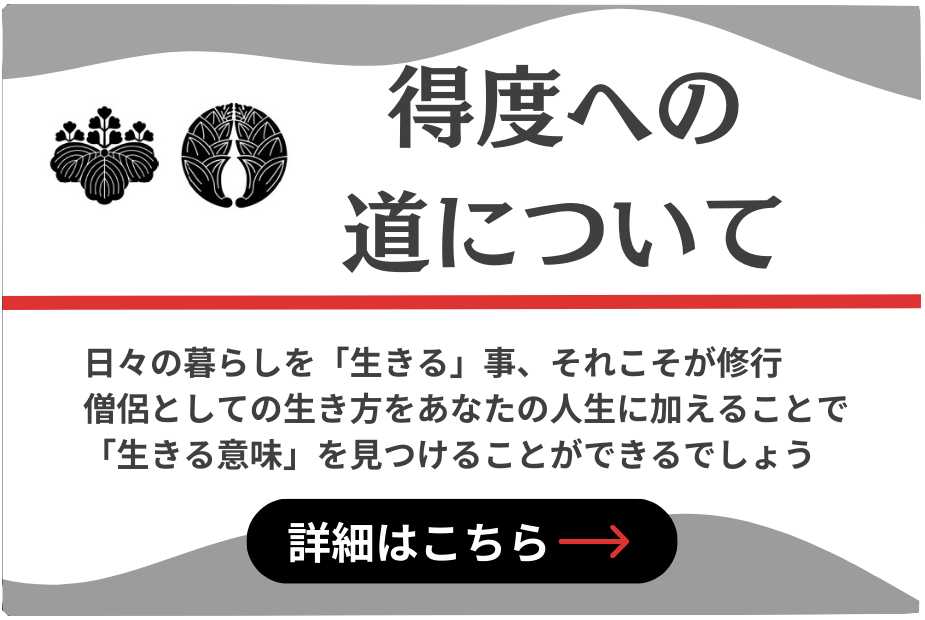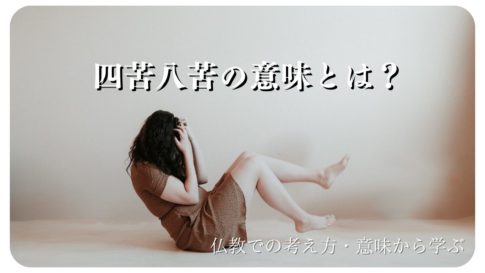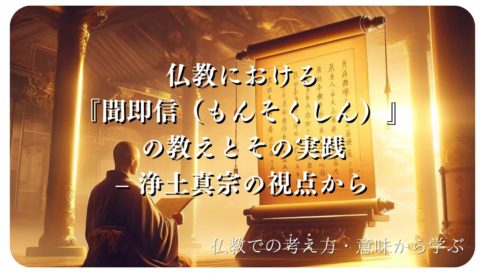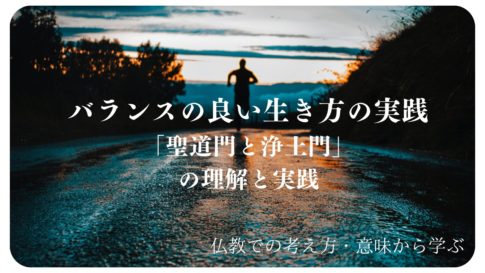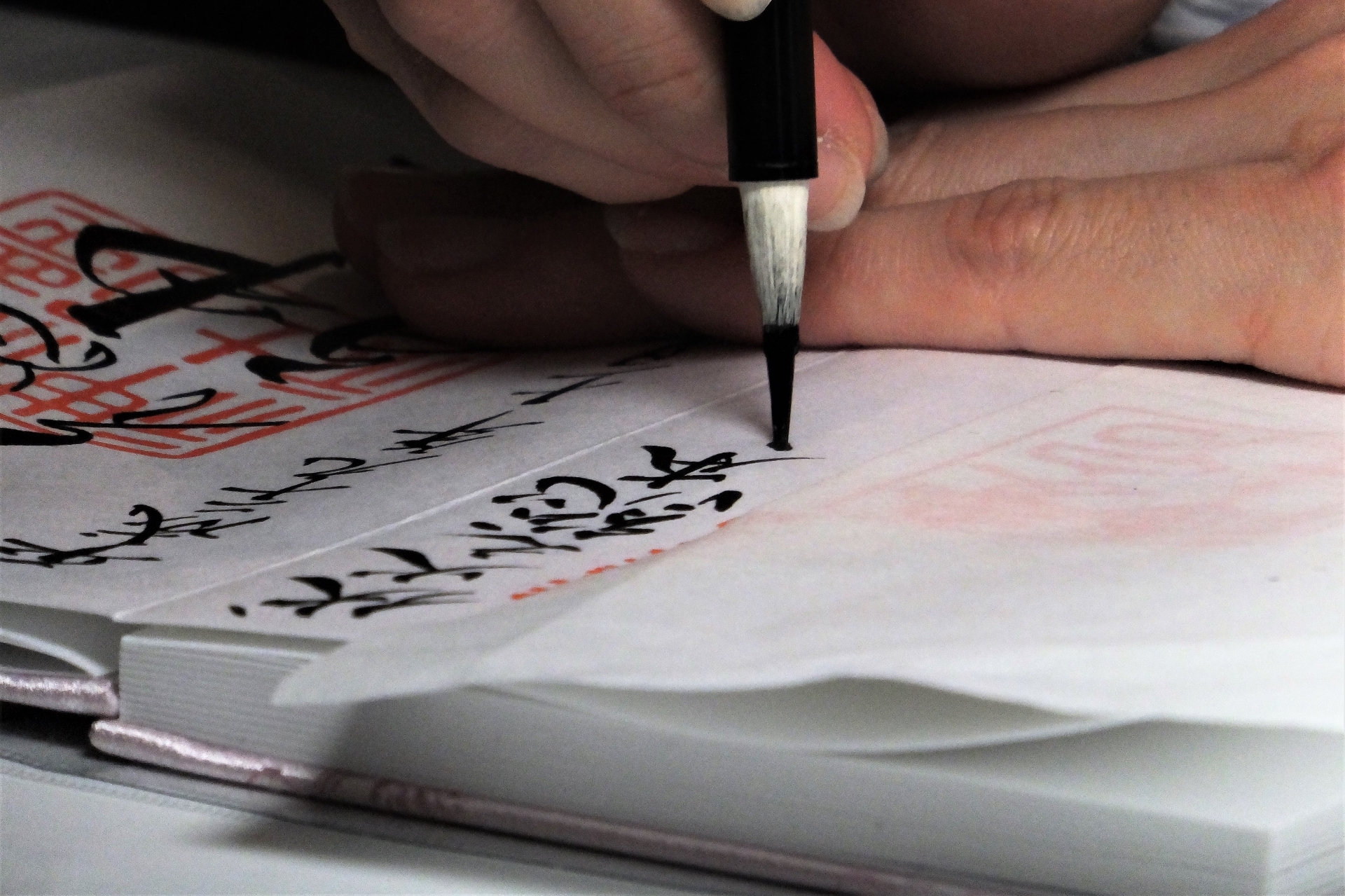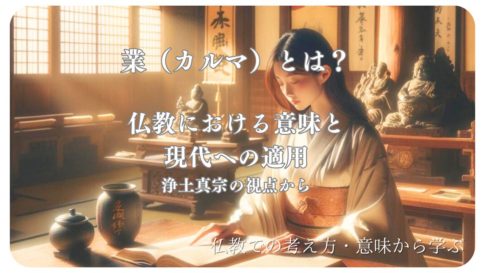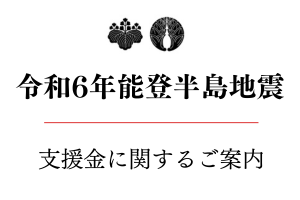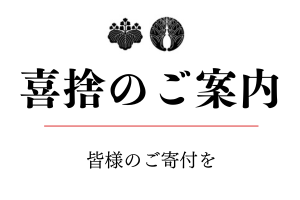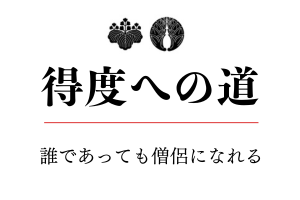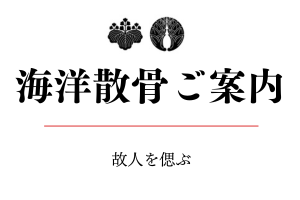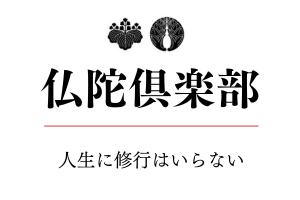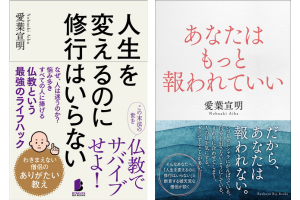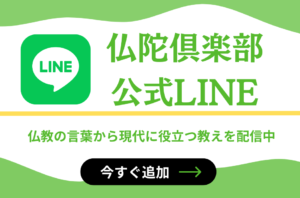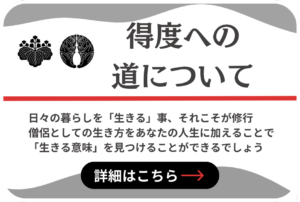目次
「諸法無我(しょほうむが)」の背景と重要性
「諸法無我」は仏教の核心的な教えの一つであり、すべての存在や事象は独立した永続的な自我を持たないという意味を持ちます。
これは、我々が「私」として認識するものが、実際には多くの要因や条件によって形成されており、恒常的な存在として捉えることができないという考え方です。
この教えは、人々に自我や執着からの解放を促すものとして伝えられています。
現代社会は個人主義が強まり、自我やアイデンティティ(個人の価値観)に強い執着が見られることが多い。
このような背景の中で、「諸法無我」の教えは、我々に自我の相対性や非実在性を理解させ、過度な自己中心的な考えや行動から解放する手助けをするものとして位置づけられています。
「諸法無我」の本来の意味
古典的な仏教の文献、特にアガマ経典や大乗経典において、「諸法無我」とは、物事や生命、そして心までもが独立した存在として永続することはないという教えとして説明されています。
これは、すべての存在が互いに関連しあって成立しており、それ自体に恒常的な「自我」は存在しないという考え方を示しています。
「諸法無我」とは、文字通り「すべての事象や存在は無我である」という意味を持ちます。
これは、私たちが日常で感じる「私」という意識や感覚も、さまざまな要因や条件によって形成されているものであり、恒常的な「私」や「自我」は存在しないという考えを示しています。
この教えは、我々の執着や苦しみの原因となる自我の観念を超え、真の自由や平和を得るための指針となります。
現代の言葉に「諸法無我」を置き換えると?
「諸法無我」という古典的な言葉を現代の言葉に置き換えると、「無自我」や「非自己中心」といった言葉が近いでしょう。
例えると、「個別の存在に固定された自我はない」という概念として捉えることができます。
これは、現代の社会や生活の中で、自己を中心に物事を捉える傾向から、より相対的な視点で物事を見る考え方を示唆しています。
現代の哲学や心理学においても、「諸法無我」に類似した考え方や概念が提唱されています。
たとえば、心理学における「自己の流動性」や哲学の「存在の相対性」などは、「諸法無我」の教えと重なる部分が多いです。
これらの概念は、人々が自己や他者、そして世界との関係性をより柔軟に捉える手助けをしています。
無我の概念いついては、以下の記事も参照ください。
シチュエーション別「諸法無我」の理解
日常生活での諸法無我の感じ方
日常生活の中で「諸法無我」を感じる瞬間は数多くあります。
例えば、自分が一貫して持っていた価値観や信念が変わる瞬間、あるいは他者との関係性が変動する時などです。
これらの瞬間に、私たちは自我の非実在性や変動性を直接に感じることができます。
ビジネスやキャリアにおける諸法無我
ビジネスの世界やキャリアの中でも「諸法無我」の教えは役立ちます。
特に、変化の激しい業界や職種では、固定的な自我や価値観に囚われず、柔軟に変化に対応することが求められます。
このとき、「諸法無我」の考え方を取り入れることで、変化を恐れず、それをチャンスとして捉えることができます。
人間関係や感情の中の諸法無我
人間関係や感情の中にも「諸法無我」の教えは深く関わっています。
愛や友情、家族との絆など、人間関係は絶えず変化していきます。
この変化を受け入れ、それを自然な流れとして捉えることで、深い人間関係を築き、心の平和を保つことができます。

「諸法無我」を日常に活かす方法
諸法無我の受け入れ方: 心の平穏を求めて
「諸法無我」という教えは、我々が日常で感じる自我や個性、価値観が恒常的で不変ではないと示しています。
この教えを受け入れることで、日常のストレスや悩み、対人関係の摩擦を和らげ、心の平穏を求める手助けとなります。
変化や出来事を個人的な「自分」の問題として捉えるのではなく、それらを宇宙や生命の大きな流れの中の一部として受け入れることが、心の平和への第一歩となります。
自我との向き合い方: 真の自己理解へのヒント
日常生活の中で我々は数多くの役割や責任を担い、それに基づいて「自分」というアイデンティティを形成しています。
しかし、「諸法無我」を理解することで、これらの役割やアイデンティティが恒常的なものではないことを認識し、真の自己を見つめ直すヒントを得ることができます。
自分自身の思いや感情、行動を客観的に観察することで、自我との向き合い方を新たに模索することが可能となります。
諸法無我をポジティブな視点でとらえる方法
「諸法無我」の教えは、初めて聞くと否定的や消極的に感じるかもしれません。
しかし、この教えをポジティブな視点で捉えると、日常の出来事や変化をもっと自由に、そして前向きに受け入れる力が生まれます。
変化や流転を「新しいチャンス」として受け止め、自我の束縛から解放されることで、真の自由や喜びを感じることができます。

「諸法無我」を理解し、生き方に取り入れる重要性
現代の忙しい生活や情報過多の中で、「諸法無我」の教えは、心の安定や平穏をもたらす指南となります。
物事や出来事、人々との関係性を相対的に捉え、自我の固定観念から解放されることで、現代人としての生き方の中に新しい視点や考え方を取り入れることができます。
「諸法無我」の教えを日常生活に活かすための具体的な方法として、以下のようなアプローチが考えられます:
- 瞑想やマインドフルネス: 自分自身の心や感情を静かに観察することで、「諸法無我」を実感する。
- 日常の出来事を記録: 日記やジャーナリングを通じて、日常の出来事や感じたことを記録し、それを通じて自我やアイデンティティの相対性を理解する。
- 他者との対話: 他者との対話を通じて、自分以外の視点や考え方を知り、それを自分の中に取り入れることで、自我の非実在性を深く理解する。