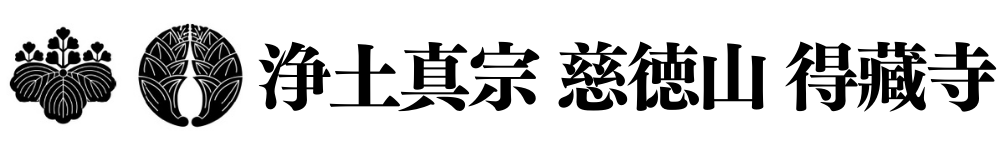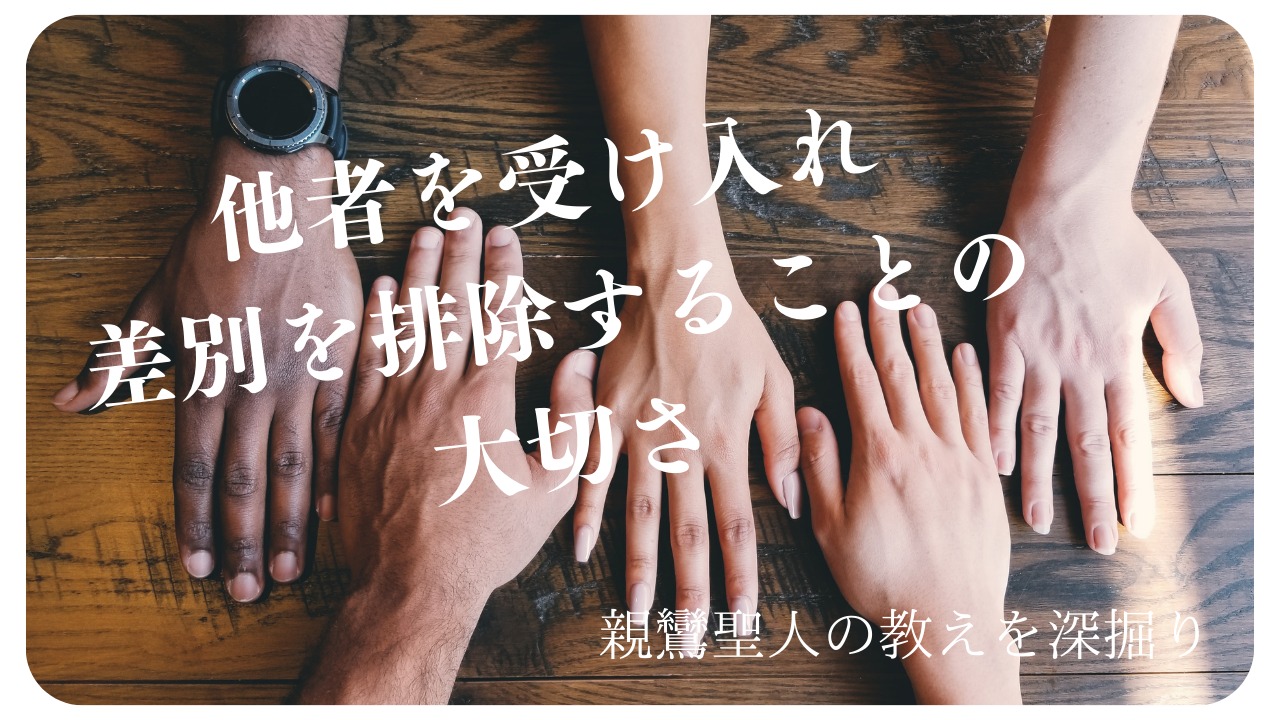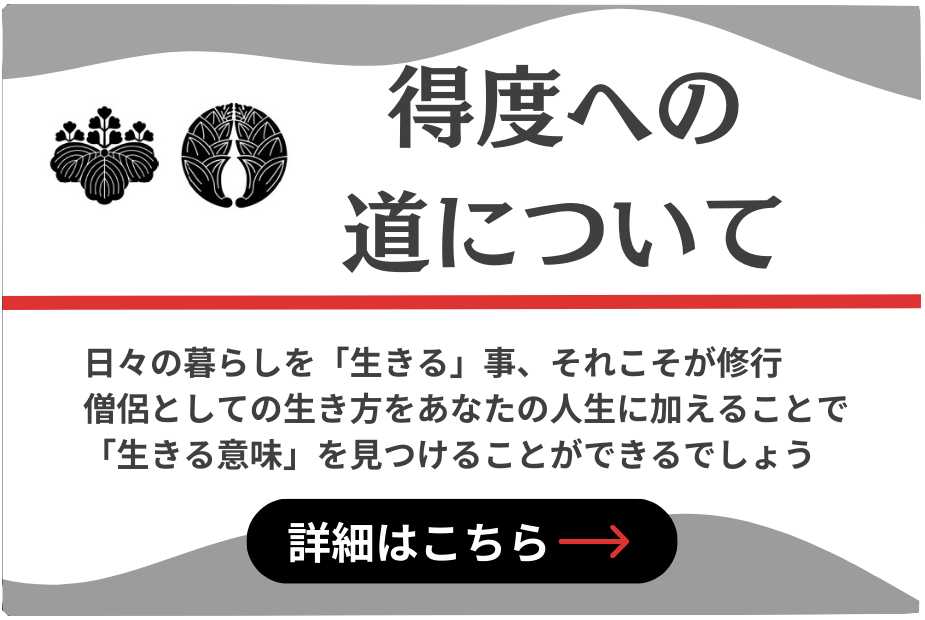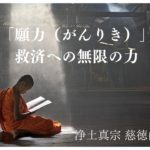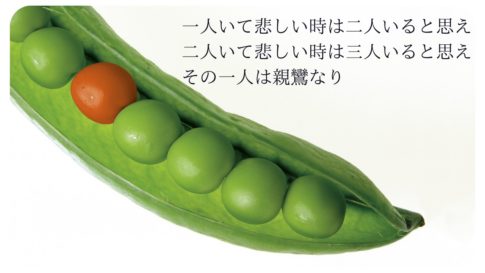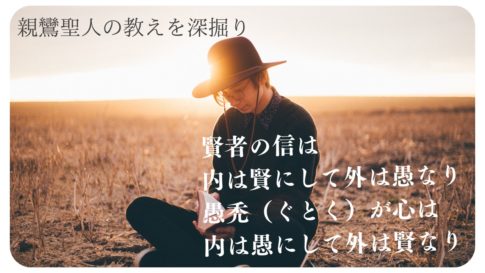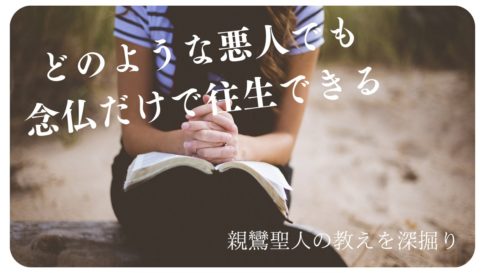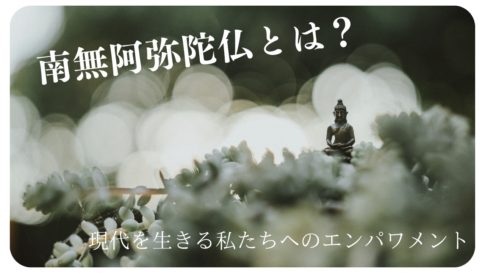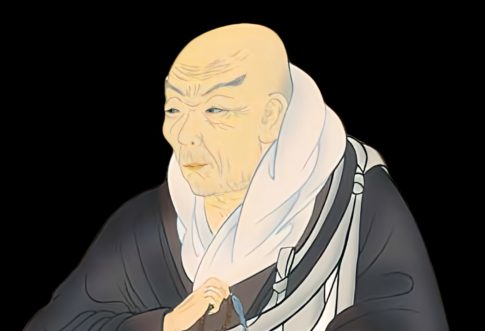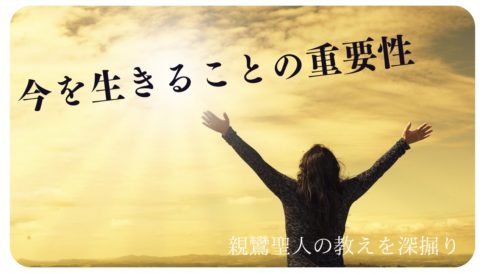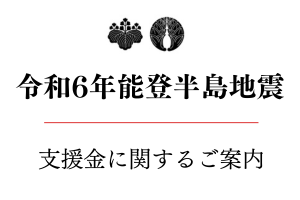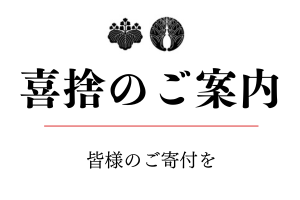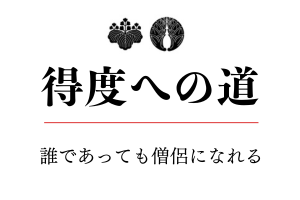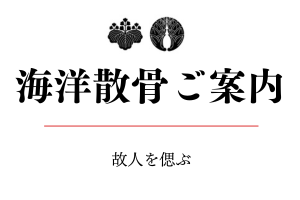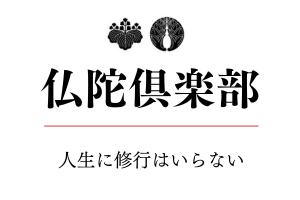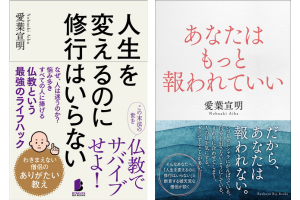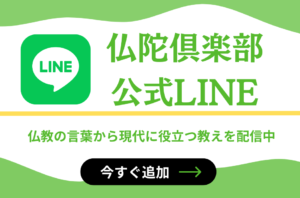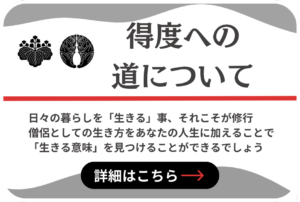目次
差別のない社会を目指す親鸞聖人の言葉
私たちが生きる現代社会には、様々な形の差別が存在しています。人種、宗教、性別、障害、経済状況など、多岐にわたる背景に基づく差別は、世界中で見られる問題です。
そのような中で、親鸞聖人の言葉「非人を差別する者こそ、真の意味での非人である」は、私たちに大きな示唆を与えてくれます。この言葉は、差別のない社会を目指す上で、非常に重要な意味を持っているのです。
古い時代の日本における「非人」とは
親鸞聖人が生きた時代、日本社会には「非人」と呼ばれる人々が存在していました。
「非人」とは、社会の最下層に位置づけられた人々を指す言葉で、特定の仕事や役割を持たず、固定した住居も持たない放浪の生活を送っていました。
「非人」は、日常の生活や祭事において特定の役割を果たすことが多かったものの、一般的には社会から疎外される存在として扱われていました。彼らの多くは、生まれながらの家系や身体的な障害、または特定の罪を犯した結果として、その地位に落とされたのです。
親鸞聖人が生きた時代の社会的背景
親鸞聖人が生きた平安時代から鎌倉時代にかけては、日本社会が大きな変動を経験していた時期でした。戦乱や自然災害が相次ぎ、社会の階級制度は天皇や貴族、武士から、農民や商人、そして「非人」に至るまで、明確に階層分けされていました。
このような社会的背景の中で、親鸞聖人は「非人」を含む多くの人々と交流を持ちました。彼の教えは、すべての人が平等であるという考えに基づいており、「非人」を差別することの無意味さや不正義を強く感じていたのです。
親鸞聖人の言葉や行動には、「非人」を含むすべての人々への深い共感と愛情が込められていました。それは、彼の信仰の核心である「平等」の思想に基づくものだったのです。
「非人を差別する者こそ、真の意味での非人である」の意味
親鸞聖人の言葉「非人を差別する者こそ、真の意味での非人である」は、当時の社会構造と価値観に大きな挑戦を投げかけるものでした。この言葉は、一体どのような意味を持っているのでしょうか。
親鸞聖人が定義する「差別」とは、人々の中に固有の価値があるという考えに基づき、一部の人々を他の人々よりも低く見ることを指します。
彼は、すべての人が平等であるという信念を持っていたため、「非人」を差別する行為自体が、真の意味での「非人」の行為であると考えたのです。
現代の言葉で解釈する親鸞聖人の言葉
親鸞聖人の言葉を現代の言葉に置き換えてみると、「他者を差別する人は、真の意味で自分自身を差別している」という形になります。
この解釈は、差別する側の人間性や価値観を問うものであり、私たちに深い気づきを与えてくれます。他者を差別するという行為は、実は自分自身の心の狭さや偏見を反映しているのだと、親鸞聖人は説いているのです。
現代社会においても、多様性の尊重や差別の排除は重要なテーマとなっています。親鸞聖人の言葉は、私たちが日常の中で他者をどのように受け入れるか、そして自分自身をどのように捉えるかということを再考するためのきっかけを与えてくれます。
現代社会における差別の問題と解決への道
現代社会は情報が溢れる時代であり、多くの差別の事例が明るみに出ています。人種、宗教、性別、障害、経済状況など、様々な背景に基づく差別が、世界中で問題となっているのです。
これらの差別の背後には、誤解や偏見、無知が存在しています。
異なる文化や価値観を理解しようとせず、自分の固定観念に基づいて他者を判断することが、差別を生み出す原因となっているのです。
差別を乗り越えるための方法
では、私たちはどのようにして差別を乗り越えていけばよいのでしょうか。親鸞聖人の教えは、その答えの一つを示してくれています。
それは、他者を受け入れ、差別を排除することの大切さです。相手を理解し、共感することが、差別を乗り越えるための第一歩となります。自分とは異なる文化や価値観を持つ人々と対話し、その多様性を尊重することが求められているのです。
親鸞聖人の言葉を現代に活かす方法は、日常生活の中で他者とのコミュニケーションを深め、多様性を尊重することです。一人一人が自分の固定観念や偏見と向き合い、それを乗り越えようと努力することが、差別のない社会を実現するための鍵となるでしょう。
親鸞聖人の教えが現代に示す意義
以上、親鸞聖人の言葉「非人を差別する者こそ、真の意味での非人である」の意味と、その背景にある仏教の教えについて探ってきました。
この言葉は、単に過去の言葉ではなく、現代社会において私たちが直面する差別の問題に対しても、大きな示唆を与えてくれます。差別の背後にある固定観念や偏見を乗り越え、他者を理解し、共感することの大切さを教えてくれているのです。
親鸞聖人の教えは、すべての人が平等であるという信念に基づいています。この考えを日常生活の中で実践していくことが、差別のない社会を実現するための第一歩となるでしょう。
皆さまがこの親鸞聖人の教えを通して、差別のない平和な社会の実現に貢献されることを心よりお祈りしています。
南無阿弥陀仏