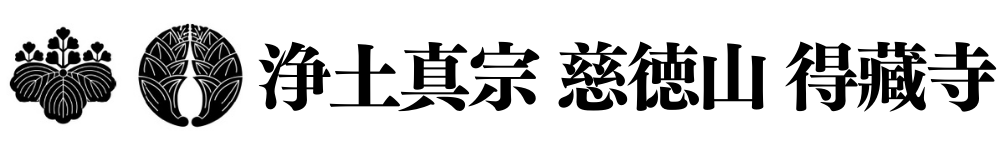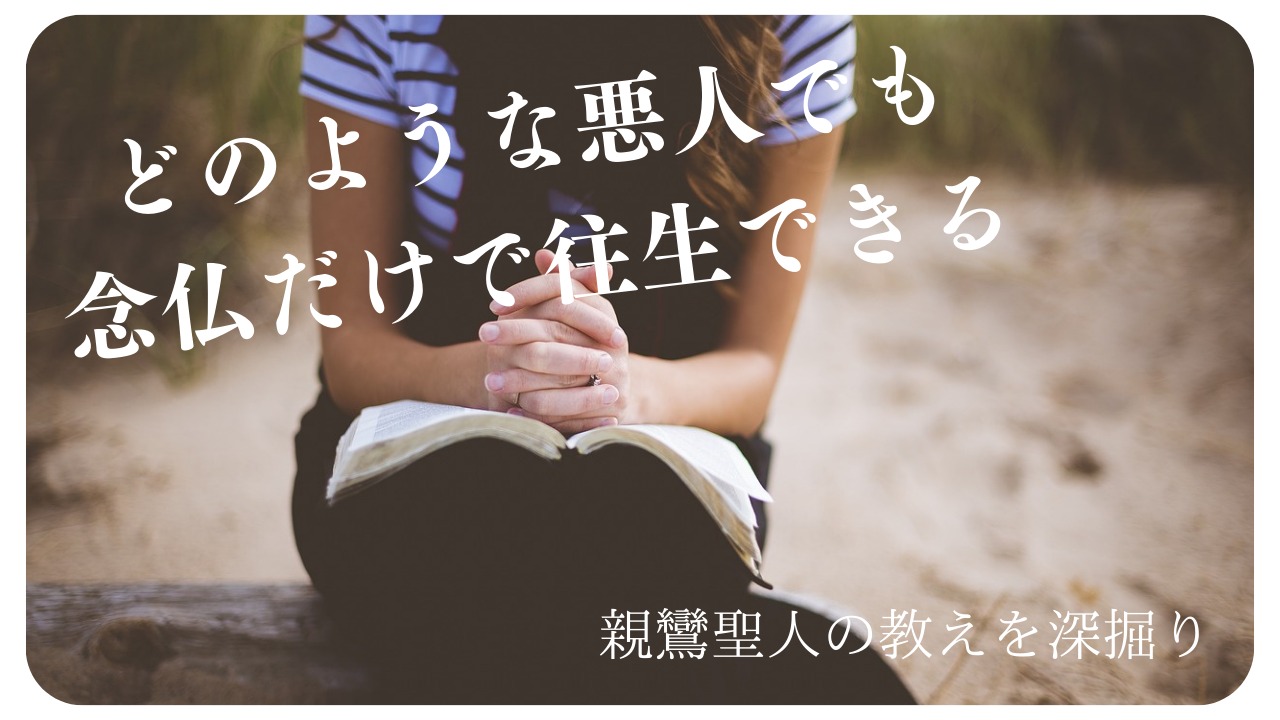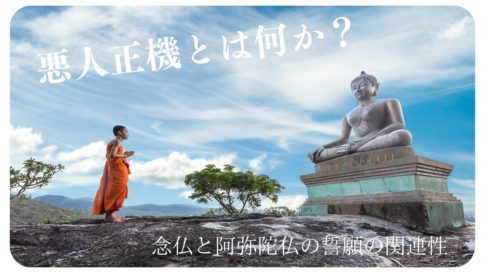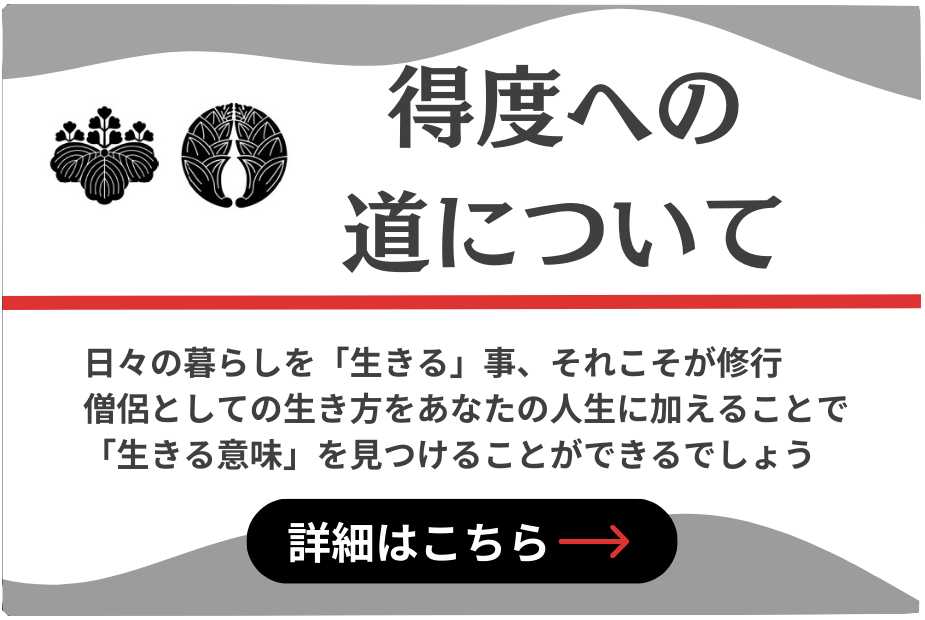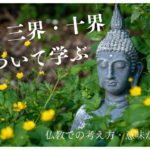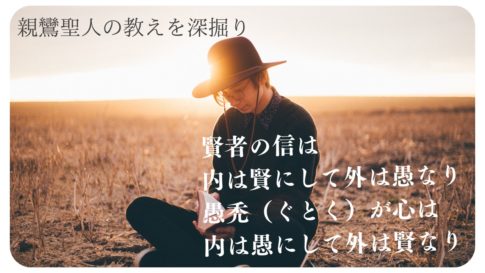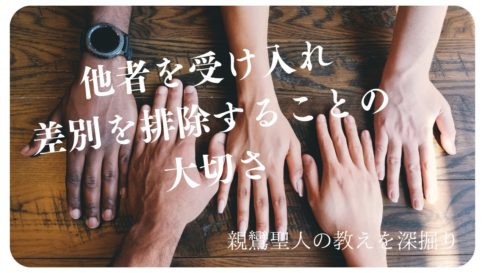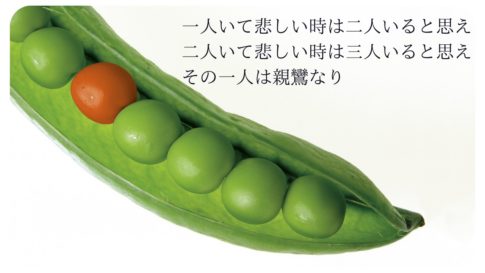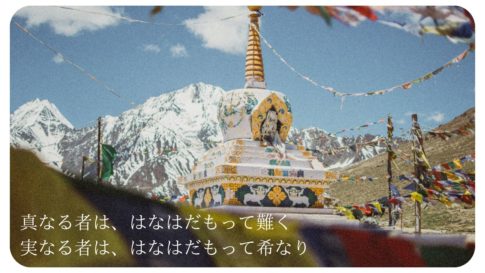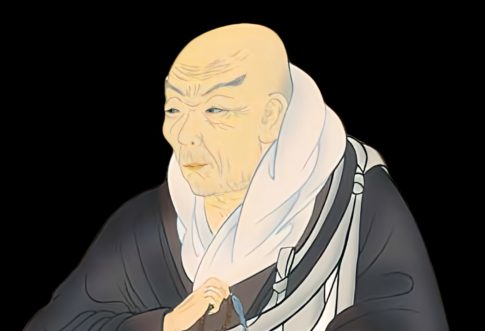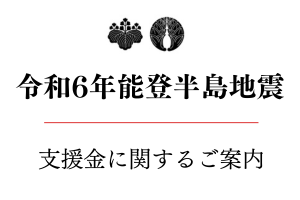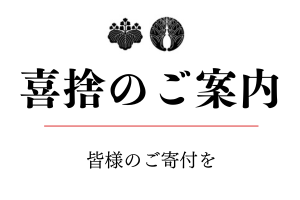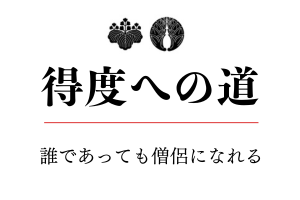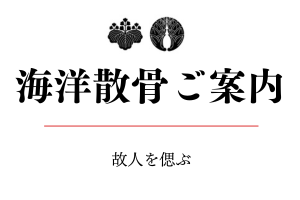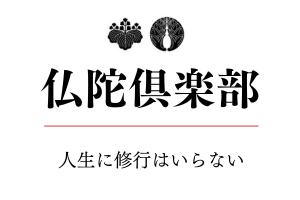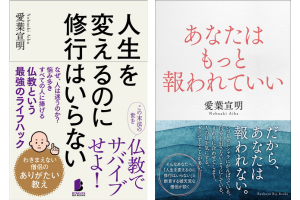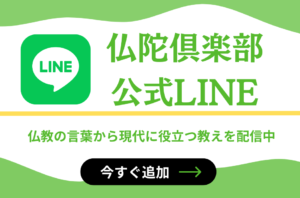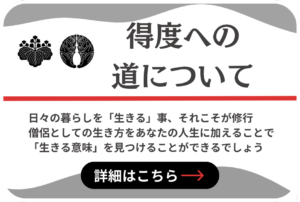目次
親鸞聖人とは?
親鸞聖人は、日本の浄土真宗の開祖として知られる仏教僧であり、彼の教えは多くの人々に影響を与えています。
彼の教えの中心には「念仏」があり、それはどのような背景から生まれ、どのように特徴的なものとなったのでしょうか。
親鸞聖人の背景
親鸞は1173年に生まれました。幼少期から仏教に興味を持ち、比叡山での修行を経て、浄土宗の教えに触れることとなります。
しかし、彼はその教えに満足することができず、自らの信仰と向き合う中で、新たな教義を築き上げていきました。
彼の教えが形成されてきた背景には、当時の日本の社会状況や、彼自身の経験が大きく影響しています。
社会的には、戦乱の時代であり、人々は安定した生活や死後の安らぎを求めていました。親鸞は、そうした人々の求める救いを「念仏」に見出し、それを広めることとなったのです。
親鸞聖人の教えの特徴
親鸞聖人の教えは、そのシンプルさと普遍性で多くの人々に受け入れられました。
その中心には「念仏」があります。
念仏とは、阿弥陀仏を称えることで、死後の極楽浄土への生まれ変わりを願うものです。
親鸞は、念仏を称えることだけで、人は救われると説きました。
他の仏教宗派との最も大きな違いは、親鸞の教えが「修行」を必要としない点にあります。
多くの仏教宗派では、修行や実践を通じて悟りを開くことが求められますが、親鸞は、ただ念仏を称えるだけで救済が得られるという考えを持っていました。
これは、当時の人々にとって非常に魅力的であり、多くの支持を受けることとなりました。
どのような悪人でも念仏だけで往生できるとは?
文字通りの意味として、この教えは、どれほど罪深い人間であっても、念仏を称えることで死後の極楽浄土へと生まれ変わることができる、というものです。
これは、人々の心に大きな安堵と希望をもたらす教えでした。
念仏の力とは、阿弥陀仏の願いにより、念仏を称えることで得られる救済の力を指します。
親鸞聖人は、この念仏の力が絶大であり、それを信じることで誰もが救われると説いたのです。
現代語訳とその解釈としては、「どんな過去の過ちや罪も、心からの信仰と反省によって許され、新たな道が開かれる」というものです。
現代社会でも、過去の過ちを乗り越えて新しい人生を歩みたいという人々にとって、この教えは大きな希望となるでしょう。
考えられる具体的なシチュエーションとして、過去に何らかの悪事を犯してしまった人が、その後の人生で深く後悔し、最期の時に念仏を称える場面が挙げられます。
この教えによれば、その人は念仏の力により極楽浄土へと導かれるとされています。
人生に修行はいらないという考え
親鸞聖人の教えの中でも特に注目されるのが、「修行不要」という考え方です。
この教えは、修行や苦行を必要とせず、念仏一つで救済を受けられるというもの。
では、この考えが生まれた背景と、現代におけるその意義について考察してみましょう。
親鸞聖人の「修行不要」の教え
親鸞聖人は、修行をせずとも念仏一つで救われるという考えを強く持っていました。
この考えの背景には、彼自身が比叡山での修行生活を経験し、それでも真の救済を感じられなかった経験が影響しています。
彼は、修行や苦行を積み重ねることよりも、心からの信仰を持つことが、真の救いとなると考えたのです。
現代における「修行不要」の意義
現代社会では、修行や自己啓発のトレンドが高まっています。
ヨガ、瞑想、断食など、さまざまな方法で心と体を鍛錬しようとする動きが見られます。
しかし、親鸞聖人の教えは、それらの修行や努力が必要ないとしています。
念仏だけでの救済が持つ意義とは、心の中で真の信仰を持つことにより、外部の方法や技巧に頼らずとも、心の平安を得ることができるというものです。
現代の忙しい生活の中で、外部の要因に振り回されることなく、心の中での信仰を大切にすることの大切さを、親鸞聖人の教えは伝えています。

まとめ:親鸞聖人の教えの現代へのメッセージ
親鸞聖人の教えは、数百年の時を経てもなお、多くの人々の心に resonating(共鳴)します。
特に、現代社会において、その教えが持つメッセージの深さと普遍性は、私たちの日常生活にどのように取り入れられるのでしょうか。
念仏の力と現代社会
現代の生活における念仏の役割は、日々の喧騒やストレスからの解放、心の平安を求める手段としての位置づけが考えられます。
物質的な豊かさや情報の過多がもたらす疲れや迷いの中、念仏を称えることで、心の安定や内なる平和を得ることができます。
念仏を称えることの真の意味は、外部の物や環境に左右されず、自らの心の中に真の救済や安らぎを見いだすことです。
親鸞聖人は、念仏の力を通じて、人々に内なる平和と真の豊かさを追求する方法を示しています。
親鸞聖人の教えを生きる
日常生活での念仏の取り入れ方としては、朝晩の瞑想時や日常の何気ない瞬間に、心の中で念仏を称えることが考えられます。
これにより、日常の中での小さな迷いや困難に対しても、心の中の指針として念仏の力を感じ取ることができます。
また、念仏を通じての人生の豊かさの追求は、物質的な豊かさや成功だけでなく、心の豊かさや人間関係の深化を追求することを意味します。
親鸞聖人の教えは、私たちが真の意味での豊かな人生を歩むための手引きとなるでしょう。